| 用途・一括名 | 物質名等 | 有害性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| かんすい | かんすいは小麦粉に柔らかく弾力性を持たせたり、色(黄色)や風味を出すために即席中華麺、スナック麺に使用される。これは炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、およびリン酸塩のうち、一種以上の混合物。 ビタミン、ミネラルを奪う可能性があり、ゆで汁は捨てた方がよい。 | ||
| 炭酸カリウム | あり | かんすいの主成分。 | |
| 炭酸ナトリウム | あり | 粘膜に対する刺激性があり、大量摂取により胃や腸などの粘膜を傷つける。 | |
| リン酸水素二ナトリウム | あり | リン酸二ナトリウムとも。 リン酸塩の過剰摂取は血中カルシウムの低下を引起こし、骨などが弱くなる。 | |
| ピロリン酸四ナトリウム | 高 | 縮合リン酸塩の一つ。かんすいの他、乳化剤、膨張剤、pH調整剤としても使用。 腎臓障害の可能性あり。 魚肉練り製品、乳製品などに使用。 | |
| ピロリン酸四カリウム | あり | 縮合リン酸塩の一つ。かんすいの他、乳化剤、膨張剤としても使用。 腎臓障害の可能性あり。 魚肉練り製品、缶詰、麺類などに使用。 | |
| 結着剤 | ハムやソーセージ、魚肉練り製品、めん類などの組織の改良などの目的で使用される。
結着剤には正リン酸塩や重合リン酸塩(縮合リン酸塩とも)が使用されるが、この長期の過剰摂取により次の弊害がある。腎臓機能低下や腎臓障害、骨の形成異常、骨粗しょう症、腎石、動脈硬化など。また、短期的にはカルシウム不足や鉄の吸収不足が起こる。 | ||
| 正リン酸塩 | あり | リン酸一ナトリウム、リン酸二カリウム、リン酸三ナトリウムなど。 | |
| 重合リン酸塩 | あり | メタリン酸ナトリウム、メタリン酸カリウム、ポリリン酸ナトリウム、ポリリン酸カリウムなど。 | |
| 消泡剤 | 揚げ油、豆腐、果実ジャム、ウイスキーなどの酒精飲料の製造・発酵工程で使用される。 | ||
| グリセリン脂肪酸エステル | 乳化剤としての働きもある。 加工助剤のため、製品には残留が残らないとされる。 | ||
| シリコーン樹脂 | |||
| 抽出溶剤 | 油脂などの成分を効率よく抽出するために使用するもの。ただし、抽出溶剤は最終食品前に完全除去されていることが前提のため表示されない。 | ||
| ヘキサン | 植物油の抽出に使用。 | ||
| アセトン | あり | ガラナ成分の抽出に使用。 | |
| ヘキサン | 食用油脂の抽出に使用。 | ||
| 凝固剤 | 主に豆腐用凝固剤のことで、大豆から作った豆乳を固めて豆腐にするために使用される。 | ||
| 塩化カルシウム | なし | 塩化カルシウムなどの塩化物。 | |
| 塩化マグネシウム | なし | にがりのこと。 | |
| 硫酸カルシウム | なし | 硫酸カルシウムなどの硫酸塩。 | |
| グルコノデルタラクトン | なし | ラクトン類。膨張剤としても使用され、塩化マグネシウムの場合よりも体積が大きくなる。 | |
| 水酸化カルシウム | 消石灰のこと。こんにゃくの凝固剤。 | ||
| 日持向上剤 | 短期間だけ微生物による腐敗や変敗を抑える目的で使用される。 実質的に保存料であるが、これは「保存料」の表示が不用のため、消費者への印象を良くするために利用されることが多いようだ。 また、保存量には使用基準が定められているが、こちらは使用基準がないという違いがある。 | ||
| 有機酸 | 酢酸、酢酸ナトリウムなど。 酢酸ナトリウムは酸味を和らげる効果があるため、酸味料や調味料(アミノ酸等)、pH調整剤などと記載することもできる。 | ||
| アミノ酸 | グリシンなど。(グリシンは調味料、緩衝剤等の目的でも使用される。なお、グリシンを多量に含んでいるものを常用すると毒性があるとされる。) | ||
| 酵素 | リゾチームなど。リゾチームは細菌を溶かす酵素で、卵白から抽出される。 | ||
| ビタミンB1 | ビタミンB1ラウリル硫酸塩のこと。 | ||
| 香辛料抽出物 | |||
| 品質改良剤 | |||
| プロピレングリコール | あり | 保湿性、湿潤性を持つことから、生めんなどの品質改良剤として使用される。 | |
| 臭素酸カリウム | 強 | 小麦粉の改良剤で、除去が原則とされる。発癌性、染色体異常など。 パンに使用。なお、強毒性や強い発ガン性から海外では使用禁止になっているところが多い。 | |
| 離型剤 | 焼き上がったパンや菓子が型離れしやすくなるように使用される。 | ||
| 流動パラフィン | 耐熱性があり酸化されにくいという特徴がある。 | ||
| ろ過助剤 | 精製ろ過工程で不純物を吸着し、ろ過の効率を高めるために使用される。 二酸化ケイ素(シリカゲル)や酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土などがあり、使用後には除去される。 | ||
【有害性表記】
-
強…発癌性や催奇形性があったり、急性毒性が非常に強かったり、食品中や人体で発癌物質に変化するもの。
-
高…発癌性や催奇形性の疑いがあったり、急性毒性や慢性毒性が強かったり、細菌やカビに対して強い毒性を示すもの。
-
なし…大量に摂取しないかぎり安全性が高いもの。
【ppm】
【ADI】
【酸とアルカリ】
【エステル】
【トランス脂肪酸】
【活性酸素】
酸素分子は大気の21%(体積比)を占める物質で、これは植物の光合成によって作られる反応性の高い物質である。
(この意味では、生物にとって植物は非常に重要な存在ということになる。このことは植物が大規模に枯渇するような状況においては無視できないことである。)
一方、大気の78%を占める窒素分子は、三重結合している分子であることから化学的に安定である。
これは、窒素分子を取込みアンモニアに変えることができる根粒バクテリアによって植物に取り込まれる。
また、雷による放電によって窒素酸化物となって雨とともに地上に降り注ぎ、植物に取り込まれる。
分子というのは結合性が満たされた状態のものであるから、原子の不対電子は他の原子の不対電子と対をなすのが普通である。ある軌道に電子が対に入る場合には、パウリの排他原理によりスピンが逆向きとなることから、対電子の全スピンは0となる。
酸素分子は糖(グルコース)が酸化される時に利用され、この反応は次のようになる。
アルコールは神経の興奮性を抑制するものであるにも関らず、脳の興奮性を高めるようになるのは脳は抑制性のニューロンが多いため。
脳のある全体的興奮性は側抑制によって速やかに抑制されるのが一般的である。
蛇足ながら、一般的に大人あるいは知識人と呼ばれる人達が否定的傾向が強いのはその現れと考えることができる。
このことは多くの場合、有効であるとしても(というのは正しい見解や事実を述べる場合を除いては間違った意見や考えの方が確率的に高いため)、真実な有害的見解や危機的見解に対する否定的意見に与し易いという意味では重大な過失を産みやすい。
例えば、「…のようなことは有り得ない」というのは何の根拠がなくても信じ込みやすいのである。
また、ストレスも活性酸素を生じさせることになる。
ストレスが生じた場合、ステロイドホルモンの一種であるコルチゾールが分泌されるが、この合成過程や分解過程で活性酸素が生じることになる。
また、アドレナリンなどの合成過程でも活性酸素が生じる。
コルチゾールはリンパ球の一種であるNK細胞(ナチュラル・キラー細胞)の活性を低下させる。
NK細胞は自己の病的細胞を認識してこれを破壊する細胞であり、この活性の低下は病気に罹りやすくなったり、癌細胞の発生や増殖を助長することになる。
【ストレス】
生物とは自己の永続的存在性を志向するものであり、したがってこれを脅かすことについては防御反応を起すことになる。
肉体の永続性を保つためには、この様々な不変性や恒常性を維持する必要がある。
これを変化させるものはストレス要因となる。
これとしては、温熱や寒冷、騒音、過労、感染、炎症などがある。
【発癌について】
癌は癌細胞と間質とから構成されるが、癌細胞は正常細胞(すなわち元の同一遺伝子を持つ細胞)が突然変異した細胞のことであり、間質は血管と結合組織とからなる。
この細胞が分裂を繰り返すことによって増殖し、癌ができるということになる。
ただし、このためには半永久的に分裂が可能なように、染色体の端にくっついているテロメアを保護するためのテロメアーゼ活性を持っていることが重要とされる。
一方、正常細胞では分裂を繰り返す度にテロメアの長さが短くなり、細胞に寿命が生じることになる。
ただし、遺伝子に変異が生じたからといって、それは必ずしも癌化するとは限らない。
癌化が生じるには特定の遺伝子において変異が生じる必要があり、それらの遺伝子は、癌化遺伝子と癌抑制遺伝子とに大別される。
癌化遺伝子は、これが活性化することによって細胞を癌化させるもので、癌抑制遺伝子の場合には、これが不活性化することによって細胞が癌化するということになる。
つまり、遺伝子変異が、癌化遺伝子の活性化や、癌化抑制遺伝子の不活性化となった場合に、細胞の癌化が生じるということになる。
癌活性遺伝子としては、アーブ-B2遺伝子、K-ラス遺伝子(細胞増殖能の昂進)などが挙げられている。
癌抑制遺伝子としては、P53遺伝子(細胞増殖の停止を行なったり、細胞死を意味するアポトーシスを誘導)、APC遺伝子(細胞増殖の抑制)、DCC遺伝子(細胞の接着能に関与)などが挙げられている。
癌細胞の特徴の一つとして細胞の遊離性があるが、これは細胞表面の接着因子の遺伝子変異が影響しているとされる。
この遊離性により、癌細胞の全身への転移が生じるということになる。
ただし、この転移は癌細胞だけであり、間質は転移しない。
間質は転移先のものを利用することになる。
さて、悪性腫瘍となる癌細胞は、そうした遺伝子変異が一気に起こるのではなくて段階を踏んで起こる、という多段階説が支持されている。
つまり、遺伝子変異を蓄積していきながら、癌化するのに必要な種々の性質を獲得していくということである。
しかし、癌化が全てこのパターンで説明できているわけではない。
癌予防としては、以下のことが挙げられる。
緑黄色野菜の他には、玉ねぎ、にんにく、豆類、バナナにも抗酸化作用があり、発癌性を抑制する効果がある。
また、香辛料や香味料として使用されるハーブ類にも抗酸化作用があり、これは総じて野菜よりも抗酸化能力が高い。
細菌にも遺伝子を傷つけて癌遺伝子を活性化させるものがある。
これとして最も多いのがクラミジア・トラコマーテスで、これは性交渉により感染する。
紫外線にはビタミンDの合成や殺菌作用、血行や新陳代謝の促進などの有用な面があるが、紫外線を長時間浴びると日焼けや皮膚の老化(皺の生成)、白内障、皮膚癌などの原因となる。
日焼けはどの波長の光でも吸収できる物質であるメラニンの生成によって生じる。
メラニンはチロシンが重合したもので(これはさらにタンパク質と結合して顆粒状となる)、これは主に皮膚の基底部にあるメラニン細胞が紫外線(UV-B)によって活性化されることで生成される。
生成したメラニン色素はUV-Aの作用によって酸化され褐色化する。
なお、メラニン色素は通常は表皮に留まるが、化粧品などの接触皮膚炎の場合には真皮に落ち込んで貯留し、濃褐色から紫褐色の強い色素沈着を起す。
これが、所謂(女子顔面)黒皮症と呼ばれるもので、この原因物質としては化粧品に含まれるタール色素の赤色219号(これに不純物として含まれるズダンⅠ)やパラベン(パラオキシ安息香酸エステルのこと。防腐剤としてよく使用される)などがある。
黒皮症は何も化粧品によってのみ起こるわけではなく、ナイロンタワシによって体をゴシゴシ洗ったり、衣類に使用された染料によって起こることもある。
老人性白内障(様々な白内障で最も多い)は日光に含まれる紫外線(主にUV-B)によって目の水晶体に発生した活性酸素によるとされ、高齢の人が日光浴をする場合には紫外線をカットするサングラスをした方がよい。
(また、ガラスはUV-B以降の紫外線を吸収し、プラスチックはガラスよりも透過率が低いためUV-Aも減少させ、度の入っていない眼鏡でも保護効果があるが、完全ではない。)
高齢者にそれが多くなるのは、活性酸素を無毒化するSOD(タンパク質の一種)やカタラーゼなどが40才を過ぎた頃から減少していくためのようだ。
そこで、活性酸素を除去する抗酸化ビタミンやフラボノイドなどを摂取するのがよい。
近年では冷蔵庫やエアコンなどから排出されたフロンガス(フロンとはクロロフルオロカーボンのこと)がオゾン層を破壊するようになった。
このため、南極付近ではオゾン濃度が減少し、オゾンホールができるようになった。
同様なことは北半球でも起こり、高緯度地方ではオゾン濃度が減少している。
家庭用電気製品の中で特に電磁波の強いものとしてはIHクッキングヒーターがあり、この使用の安全性が気にかかるところである。
ダイオキシンの基本的な構造は次のようになる。
上図で、5と10以外の場所には塩素がつくことになる。
例えば、2,3,7,8の場所に塩素がついたものは、2・3・7・8-四塩化ダイオキシンと呼ばれ、ダイオキシンの中で最も毒性が強い(モルモットの半数致死量は体重1kg当り0.0006mgとされ、地上最強の毒物とも言われる)。
なお、女性が化粧によって自己の外観を高めることはより多くの男性の関心を惹きつけることに効果があるとしても、このことが結婚を目的とする限りは、いずれ自己の素性が知られることからはあまり意味がない。(なぜなら、一般に認識は虚偽よりも真実の方を優先するものであり、嘘がばれた時点でその虚構に対する信が全く失われるからである。しばしば根拠のない想定や宣伝、洗脳といったものはその否定的事実によってその虚構が一瞬にして崩れ去る。)
癌化は細胞分裂が活発な場合(これは遺伝子の修復機構が細胞分裂の速度に追いつかなくなることによる)や免疫能力が低下した場合に起こり易くなることから、乳児や妊婦(胎児)、高齢者において癌の発症率が高まる。
また、人体の中でも細胞分裂が活発なものほど放射線の影響が高くなるが、これとしては骨髄や毛包(毛根を包むもの)、胃腸管を形成する細胞がある。
もし骨髄が障害されると、白血病に罹ったり、出血や感染症で死亡することがある。
因みに、癌治療においては癌細胞の増殖や転移を予防するために抗癌剤がよく用いられるが、これは癌細胞の高い細胞分裂性に着目して、これを示す細胞を破壊することを目的としたものである。
したがって、抗癌剤には癌細胞ではない細胞をも破壊するという副作用が生じる。
このような細胞としては、造血機能を持つ骨髄、胃腸などの消化器官の粘膜、発毛関連の細胞が代表的である。
【放射性物質】
放射性物質としてはラドン、放射性ヨウ素、放射性セシウムが代表的である。
最も危険な放射性物質としてはプルトニウムがあり、これは猛毒として知られているもので、極微量の吸入によって肺癌等を起す可能性が高いとされる。
(経口摂取の場合には、プルトニウムは消化管からの吸収が非常に少なく殆どが体外に排出されるため、この被爆の可能性はかなり低いとされる。)
因みに、放射線にはα線、β線、γ線、中性子線などがあるが、これらの実体は以下のようになる。
【環境ホルモン】
ホルモンは神経伝達物質と共に細胞間情報伝達物質で、細胞に対して特異的活動を指示する。
神経伝達物質の作用は局所的なもので、ニューロンから伸びる神経繊維によって接続された細胞(ニューロンや筋肉)に対してのみ作用する。
神経伝達物質のニューロンへの作用は、細胞膜においてイオン物質の透過を行なわせることにより、ニューロンの興奮を促進したり、あるいは抑制することである。
過去には妊婦にエストロゲン様化学物質であるDES(ジエチルスチルベストロール)がよく使用されたが、この胎児がこの曝露により後年、性器奇形や乳癌、膣癌、精巣癌、前立腺癌等を起すことになったとされる。
また、殺虫剤としてよく使用されたDDTも疑似エストロゲンであり、過去にはこれが大量に使用され、しかも長期間に渡って安定な物質であることから、環境中に多く存在することになった。
また、トランスや電磁石などの電気機器によく使用されたPCBも挙げられる。
これは耐熱性、不燃性、絶縁性の高さから幅広い用途があったため大量に使用された。
しかし、これを封入した容器の劣化等により気化したPCBが環境中に漏れ出したり、その廃棄物が焼却されたりして、PCBは全世界的に拡散することになった。
PCBには多くの種類があるが、この一部にエストロゲン様活性を持つものがあることが分かった。
DDTやPCB類は乳癌などのリスクを高めるとされる。
例えば、TCBは比較的低濃度で乳癌細胞を増殖させるとされる。
しかも、DDTやTCBなどのTCB類の一種は難分解性で脂肪に蓄積することから、TCBは容易にこの濃度に達し得る。
一方、内因性エストロゲンの方は数分で分解することから、乳癌への影響は蓄積し続けるこれらのエストロゲン様化学物質に比べれば弱いようだ。
ただし、日本的食習慣では乳癌のリスクは欧米に比べるとかなり低いとされるが、最近では日本でも欧米型の食習慣(特に高脂肪)に近づいていることから、やはり無視できないと考えられる。
特に、数世代経るとその影響が現れるとされるが、これは胎児期での環境エストロゲンへの曝露が関係しているようだ。
というのは、胎児期でのエストロゲン様化学物質への曝露はこれへの反応を高めるからである。
女性が乳癌に罹りやすいのは、卵巣からエストロゲン(エストラジオール)が分泌されるためとされる。
一般に、成人女性では月経周期にしたがって乳房は腫脹と復元を繰り返しているとされるが、これはエストロゲン値の上昇に応じて乳腺組織の増殖が促進されるためという。
乳癌細胞も同じく、エストロゲンによって増殖することになる。
エストロゲン様化学物質には植物由来のものもあり、これは植物エストロゲンと呼ばれる。
この影響については、オーストラリアの古くからの牧羊地であるパース近郊で見られた。
この地では羊に深刻な生殖障害が現れたが、この原因を調べた結果、地中海地方から導入したある種のクローバーを羊が食べていたためであることが分かった。
なお、欧米において乳癌の発生率が高いのは、主に高蛋白質・高脂肪(疑似エストロゲンの多くが脂質に蓄積される。また高カロリーでもある)・低炭水化物(食物繊維を含む)という食生活が関係しているとされる。
つまり、その食習慣によって腸内からのエストロゲンの再利用が高まるためのようだ。
【H-LD症】
さて、理性的抑制性が弱く感情表出が強くなる傾向は(脳の状態としては興奮性ニューロンの働きが強くなり、かつ抑制ニューロンの働きが弱くなった状態か、抑制ニューロンを働かせる興奮性ニューロンの働きが弱くなった状態と考えることができるだろう)、食物にも原因が求められる。
これとして砂糖(これは血糖値を急上昇させる代表的精製糖である。またこれはこの代謝にカルシウムを必要とすることから、砂糖の過剰摂取は骨減少を引起こすことにもなる?)や、グルタミン酸ナトリウム、着色料のタール色素などが挙げられるだろう。
【リステリア症】
リステリア菌は土や水の中など自然界に広く存在し、これとの接触を回避することは難しい。
したがって多くの動物はこれと接触し、動物は病気になることなくリステリア菌を運ぶようになる。
日本では妊婦は刺身や寿司を食べてはいけないと言われないが(この理由は日本ではリステリア症が年間100例未満と推定されるようにかなり稀なためか、これに罹患したとしても風邪と間違われているためと考えられる)、海外では妊婦は刺身や寿司を避けることが指導されている。
【界面活性剤】
有害な主な助剤としては以下のものがある。
シャンプーにも合成洗剤が含まれているが、これを直接頭皮にかけて洗うことは、毛根細胞を破壊して抜け毛やかさぶた、白髪の原因になるとされる。
よく頭頂部が薄くなった人を見掛けるが、これはシャンプーやリンスが原因と考えられる。
また、合成洗剤でシャンプーをすることにより、髪がサラサラになり、髪が綺麗になった印象を与えるが、これは実のところ毛髪のキューテクル(毛小皮)が破壊され、毛髪がボロボロになったことが理由である。
合成洗剤シャンプーで特に気をつけるべきことは、それが目に入ったり、鼻や口に入らないようにすることである。
もしそれが目に入った場合には角膜が白濁し、失明することにもなる。
合成界面活性剤は化粧品や歯磨き剤にもが含まれているため、これらの継続的使用には注意が必要で、歯磨き剤の場合には舌乳頭などの細胞が破壊されて多少なりとも味覚障害が起こるとされる。
なお、合成界面活性剤は食品(パン、マーガリン、インスタントラーメン、アイスクリーム等)にも使用されていて、このことは大きな問題があるのではないかと考えるかもしれないが、経口の場合には消化器官を通過して排泄されるため、この影響は皮膚からの浸透の場合と比べれば小さいとされる。
しかしながら、次の誤飲事故も起っている。
それは、1962年の東京で起きた「ライポンF」誤飲中毒死事件である。
合成洗剤から石鹸洗剤に切替える場合の注意点としては2つある。
一つは石鹸は弱アルカリ性であるため、アルカリに弱い絹や羊毛(ウール)製品の洗浄には向かないことである。
(塩基性の水溶液にはたんぱく質を溶かす性質があり、たんぱく質でできている絹や羊毛を溶かすことになる。したがって、これらの洗濯に限り中性の合成洗剤を使用した方が良いことになる。)
もう一つは、石鹸は硬水では洗浄力が落ちることである。
(なお、硬水用にはカスティール石鹸を用いれば良いとされる。)
しかし、日本の場合には河川が軟水であるため、この欠点は除外される。
一方、欧米などでは河川は硬水となるため、石鹸の洗浄力が落ちることになる。
それらの石鹸の欠点や、石鹸よりも合成洗剤の方が安価に製造できることもあり、世界的には合成洗剤が使用される風潮が強まったが、日本においては特に合成洗剤を使用する必要がないことから、健康及び環境への悪影響を考えると多少割高となっても石鹸を使用する方がよい。
(欧米や日本などの先進国では今や合成洗剤を使用するのが主流であり、時代遅れな石鹸を使用するのは後進的であるというのは全く見当外れな批判である。)
【農薬】
農薬に使用される化学物質には発癌性があったり(食物に因る発癌の殆どは野菜や果物などの残留農薬が原因とされる)、催奇形性があったり、免疫力を低下させるなどの弊害があるが、農薬を使用して育てた野菜や果物には残留農薬が含まれ、これらを水で洗っても完全には除去されないため、この食品の摂取は農薬への曝露を引起こす。
農薬は、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調整剤に大別される。
以下の表は、発癌性や催奇形性のある農薬あるいは危険性の高い農薬について、主な化学成分系列別に分類して示したものである。
この表の「性質」欄は順に、急性毒性、魚毒性、発癌性、催奇形性を表わす。
ppmとは"parts per million"の略で、すなわち百万分の1単位のこと。百分率に換算すると、
1ppm=0.0001%
となる。なお、ppbというのもあり、これはppmの1000分の1のこと。bはbillion(10億)の略。
体重1kgあたりの一日摂取許容量のことで、添加物の安全性を言う場合によく用いられる。
発癌性などの慢性毒性が出ない量に1/100程度の安全率を乗じて設定される。
アルカリとは塩基性を示す物質のこと。
酸と塩基の現代的な一般的定義は次のようになる。酸とは電子対受容体のことで、塩基とは電子対供給体のこと。
たとえば、水素イオンは電子受容体なので酸となる。
一般に酸と呼ばれるものは水素を持っていて、これを与えたり、奪ったりすることで化学反応が生じることになる。
(特にOH基やNH基、SH基をもつものは大抵が酸となる。)
したがって、酸と塩基は次のようにも定義される。
酸とは水素イオンを与えることができる物質のことで、塩基とは酸から水素イオンを奪うことができる物質。
エステルとはアルコールと酸(特にカルボン酸)とが脱水反応(-OH基と水素イオンが結合して取れること)によって生じた化合物のこと。
一般にアルコールとはOH基を含む化合物の総称で、メタノール(有毒)やエタノール(これが通常言われているアルコール)が代表的なもの。
(これらは最も単純なアルコール類で、分子が小さいために血液脳関門を通り抜けて脳に進入し、酔いを引起こすことになる。)
他には、グリセリンや糖などがある。
カルボン酸はカルボキシル基(-COOH)を含む化合物のことで、脂肪酸はカルボン酸の一種。
マーガリンやショートニング(shortening. 練りこみ専用の固形油脂のこと)にはトランス脂肪酸が含まれている。
これらは植物油の不飽和脂肪酸を水素添加によって飽和脂肪酸に変えたもので、本来の植物油脂とは異なる。
また、近年ではマーガリン類のファットスプレッドというものもよく使用されるようになったが、これとマーガリンとの違いは油脂の含有率の違いで、油脂の含有率が低いものがファットスプレッドと呼ばれる。
また、マーガリン類から派生したブレンドスプレッドというのもある。
マーガリンやショートニングは食品の加工用に広く用いられるようになったのだが、化学的に製造されたこれらの加工油脂は体に有害性があるとされる。
これは、天然にある脂肪酸はシス型なのに対してマーガリン等の場合にはトランス型のものができてしまうことによる。
(また、業務用途の調理用油にも含まれ、知らずに摂取していることが少なくないようだ。)
つまり、これが細胞膜に多くあると、細胞膜が弱くなったり(或いはこの働きが悪くなったり)、有害物質が皮膚から進入しやすくなったり、アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎を引き起こす恐れがあるため。
また、悪玉コレステロールの増加、酵素の働きを阻害、心筋梗塞や肥満、血行不良、EDの原因になるなどの弊害もある。
欧米諸国ではトランス型脂肪酸の含有量が規制されたり、その含有量の表示が義務づけられた。
このため、それを含まない「トランス・ファット・フリー」が販売されるようになった。
しかしマーガリン等の加工油脂を控えても、トランス型脂肪酸は植物油にも含まれるようになっていて(これは溶剤を用いて作られるようになったため)、これからの摂取もある。
また、業務用でよく使用される硬化油には特に多く含まれ、これを用いて揚げた食品にはトランス型脂肪酸が多くなっている。
トランス型脂肪酸の一日最大摂取量は2gとされるが、家庭用のマーガリンには平均して10%程度含まれていることや、よく食べるパンやケーキ、クッキーなどの食品にマーガリンやショートニングが使用されていたりするため、容易にこの摂取上限を超える恐れがある。
なお、パンなどにマーガリンやショートニングがよく使用されるのは、味や食感を改善したり、ショートケーキのように柔らかくすることが目的のようだ。
酸素よりも反応性の高い元素としてはフッ素があるが(フッ素が電気陰性度が最も高く、電子を奪いやすい、つまり酸化力が最も強い)、この単体のフッ素分子は存在量が低すぎる上に反応性が高すぎるため、生体にとっては毒物となるだけで利用されることはない。(もっとも歯の象牙質を強化するためにこの化合物(フッ化ナトリウム)が利用されることもあるが、この有害性も指摘されている。)
酸素分子はO=Oというように(原子価結合法によって)単純に結合しているものと考えられていたが、量子力学の発展によってこの結合が分子軌道法で考えられることになり、これによれば2個の不対電子を持つラジカル分子であることが分かった。
そして、不対電子を持つことから、この分子が磁性を持つ理由が説明された。
そのように酸素分子は活性が高いのであるが、これ自体は活性酸素ではない。
活性酸素というのは、酸素分子よりも活性の高い分子のことで、これとしてはスーパオキシドアニオン(O2-:アニオンとは陰イオンのことで、これは省略されることもある)、過酸化水素(H2O2… H-O-O-H)、ヒドロキシラジカル(・OH)、一重項酸素(1O2)がある。
一重項酸素というのは、この分子の最上位のエネルギー軌道であるπ*反結合性軌道のそれぞれに入る電子(このためスピンは同じ向きに揃う)が、この一つの軌道に入った状態のもので(このためスピンは反対向きになり、これらの全スピンは0になる。このことは紫外線などのエネルギーによって電子が励起されることで起こる)、これはエネルギー状態が高くなることから、酸素分子よりも反応性が高くなる。
活性酸素の中ではヒドロキシラジカルの反応性が最も高く、脂質やタンパク質、糖質など生体を構成する全てのものと反応する。
発生量ではスーパオキシドアニオンが最も多いが、他の活性酸素に比べると反応性は低い。
一重項とは全電子のスピン量子数が0のものを言う。
通常の酸素分子の場合、これは例外的に全電子のスピン量子数が0ではなく1となることから、三重項となる。(なお、スピンの場合、他の量子数とは違って半整数の1/2または-1/2の値をとり、1/2単位となる。)
酸素分子は上位の分子軌道(これより下位の軌道では結合性と反結合性とでほぼ相殺するため、結合性を考える上では無視してよい)で反結合性軌道に入る電子があるものの全体としては結合性であり、分子として存在できる。
つまり、呼吸における酸素分子の利用とは、分子全体がよりエネルギー状態が低いもの(これとしては二酸化炭素や水が代表的)に変化することによって差分のエネルギーを得るということである。
(一方、光合成の場合は反応が逆になる。この場合のエネルギーは太陽からの輻射エネルギーとなる。
また、このとき植物が利用するものは糖となる。)
しかしながら、体内に取り込んだ酸素の約2%が活性酸素になるとされる。
また、活性酸素は紫外線やストレス、激しい運動、食物、飲酒、喫煙、細菌やウイルスなどの病原体の侵入などで過剰に生じることになる。
病原体の侵入によって活性酸素が増えるのは、これを撃退するために白血球の一種である好中球が活性酸素を放出することによる。
(好中球やマクロファージは病原体を一般的に撃退するもので、リンパ球は抗原認識後にこの能力を発揮する。傷口から病原菌が侵入して化膿した際の膿というのは、病原菌との戦いで生じた好中球の死骸である。)
しかし、活性酸素は自身の細胞をも傷つけることになる。
アルコールや食物から取り込んだ食品添加物や残留農薬、重金属など生体にとって無用なものが肝臓で処理される際、薬物代謝に従事するチトクロームP450という鉄酵素が主として働くことになる。
これは処理対象の基質とともに酸素と結合して処理するのだが、このときに1個の電子を必要とする。
もしこれが提供されないと、この鉄酵素は基質を手放すとともに酸素を活性酸素として放出する。
アルコールは脳に入って酔いを生じさせるが、この本質は神経細胞の興奮性を低下させることによるものである。
このことによって脳の興奮性を高めたり、怒りや不安などの過剰な興奮を鎮めたりする効用があるが、これは心理的な有効性であって、生体が特に必要とするものではない。
そのように、アルコールは脳の抑制性を弱めて興奮性を高めるものの、限度を超えると興奮性が全く低下することになる。
そして、限度を弁えない酒飲みはそのために不快になってしまうのである。
(飲酒の快楽は節度を守ってこそなのであるが、飲酒はこの制御性を失わせるという意味で自己矛盾的である。)
ただし、脳の興奮性は無からは生じない。したがって、飲食や音楽などによって脳を刺激する必要がある。また、人と心理的に結合することも有効だろう。おそらく、これを目的として騒々しくすることが多いのだと考えられる。彼等がしばしば行なう無意味な行動はこのことによって合理的に説明され得る。
なお、意味のない行動を繰り返すため彼等は愚鈍に思えるのだが、実は狡猾だったということになる。
それを回避するためには、その策略に嵌まらないことが肝要である。
しかしながら、そのような人でも自己の願望に対しては過信を産みやすいのも事実である。大人といった常識を弁えた人でも容易に騙されることがあるのは、相手の言動からというよりは自己の願望から生じていることが多いといえる。
また、構成的論述も相手の考えに嵌まりやすいといえる。
というのは、自己によってある考えが構成された場合には、それを信じる傾向が生じるからである。
例えば、「AならばBである」ということを考えるためには、とりあえずAが真であるということを受入れる必要がある。そのようにある仮設を元にして論理が展開され、結果が事実と適合する場合、自然にその仮設を真実であると思い込んでしまうのである。
その極端な例としてはニュートン力学やマクスウエルの方程式に代表される電磁気学が挙げられる。
これらは非常によく現実と適合していために、原子時代を迎える前の19世紀以前の科学者達はこの絶対的真実性を疑わなかった。
しかしながら、ニューロン力学などの古典力学を原子の振舞いに適用すると矛盾が生じることが分かり(荷電粒子である電子が原子核の周りを運動すると、この加速度運動により電磁波が放射され、電子は速やかにエネルギーを失い原子核に落ち込むことになるが、これは原子の実態と合わない。なお、電子が原子核の周りを回っているという原子像はラザフォードの実験によって確認された)、この真実性が揺らぐことになった。
この前には光速度不変性により揺らいでいたが(この観測事実により相対論が提唱され、空間、時間及び質量の絶対性が放棄された)、この揺らぎは原子の観測によって決定的になり、古典力学は真実の座から降りることになった。
一点の曇りもなく真実であるということが自らの崩壊を招くことになったという意味では象徴的である。
このことは絶対的真実に到達することができない経験的科学に限らず、構成的科学である数学においても起った。
これはゲーデルによる不完全性定理によって証明された。
これは、数学の完全な公理化は不可能である、ということを証明したものだった。
(このことは、論理的構築の前提である公理の選定には任意性があり、この選択的必然性を保証するものは何もない、ということによるのではないかと考えられる。例えば、幾何学の公理的理論であるユークリッド幾何学も非ユークリッド幾何学が現れたことにより、この公理の絶対性が否定された。公理の正当性は、これが証明しようとする事実等の集合と関係性があると考えられる。)
したがって、論破を回避するためにはできるだけ曖昧あるいは意味不明に述べるということが効果的でありそうした論述は多いが、意味もなく専門用語を多用するならば、それは自分の学識を誇りたいか、相手をケムに巻こうという意図が隠されていると考えるべきだろう。
(知らないことを考えるためには、とりあえずその前提や知識を真であると考える必要があるのだから。)
また、外部の脅威に対しても対処する必要がある。
人もまた動物であり、動物界の常である弱肉強食ということに対処する必要がある。
つまり、他の動物に襲われるという事態に対処する必要がある。
そのような事態が発生した場合、肉体はどのように対処する必要があるかといえば、脳や筋肉の活動性を高めることが第一に求められることになる。
これらはエネルギー源としてブドウ糖(グルコース)を利用するため、肉体はこの供給を高める必要がある。
このためには、肝臓に蓄積したグリコーゲンを分解してブドウ糖に変換して血管に放出するのだが、この指令を行なうものが副腎皮質から分泌されるコルチゾールと呼ばれるホルモンである。
このホルモンの分泌指令は、視床下部の下垂体から分泌されるACTHと呼ばれるホルモンである。
また、血管についてはこれを収縮させて血圧を高める必要がある。
この指令を行なうものが、副腎髄質から分泌されるアドレナリンやノルアドレナリンと呼ばれるホルモンである。
ストレスによって活性酸素が生じるというのは次のことによる。
生体は様々な恒常性を維持するものであり、これを変化させるものはしばしばストレスとなる。
例えば、肉体的ストレスとしては
また、生物は外部の環境に依存して生きているものであり、生存環境の変化に対して心理的ストレスが生じることになる。
これとして代表的なのは、危険な動物に出会った時に生じる肉体的変化である。
(このことは生存性に対する危機認識によるものといえ、人間の場合にはそれ以外にも様々な危機認識が生じることになる。また、好適な生存条件に対する喪失感も心理的ストレスになり得る。)
これに対しては戦うか素早く逃げるかの何れかの対処が要求されるが、このためには脳および筋肉の活動性を高める必要があり、このエネルギー補給として血糖値を高める必要がある。
また、血圧を高めてこの循環性を高める必要もある。
病原体、酸・アルカリ、毒物、打撲などによる炎症、紫外線・放射線などがある。
また、コルチゾールの放出は炎症反応を抑制するため。
遺伝子はDNAという二重螺旋の構造を持っているが、この構造は水素結合という比較的弱い結合によって維持されている。
(例えば、小さな分子からなる水が常温で液体となっているのは、分子間で水素結合が働いているからである。これは水素側の共有電子雲が電気陰性度の高い酸素側に引きつけられていて、水素側が正電荷を示すのに対して、酸素側の共有電子雲は酸素側に強く引きつけられるために負電荷を示し、これらが近くに存在する場合には静電気的引力が働くということになるからである。)
このため、遺伝子は外部の作用を受けやすい(このことは主に細胞分裂の際の、細胞の核の中の染色体がほどけてDNAが複製されるとき)。
特にフリーラジカルの影響を受けやすい。
癌化遺伝子の活性化は、点突然変異(塩基一つの置換)、遺伝子増幅、遺伝子再構成などによって起こるとされる。
癌化抑制遺伝子の不活性化は、点突然変異、塩基の欠損または挿入(遺伝子は4種の塩基の並びで構成されているが、これから20種のアミノ酸を対応させるためには、塩基3つが必要となる。これはコドンと呼ばれる。
しかし、その並びに欠損や挿入が生じた場合には、その組合せがずれてしまうことより、全体的にコドンが変化することになる。
したがって、生成される蛋白質が全く異なったものとなることより、その影響は大きい)、染色体の欠損などによって起こるとされる。
しかし、そうした変異だけでは癌細胞の増殖が進展するわけではない。
というのは、細胞が周囲との調和を乱して増殖を続けた場合、この細胞はアポトーシスという機構によって死滅してしまうものだからである。
(これは癌抑制遺伝子(というよりは分裂抑制遺伝子という方が妥当があるが)の一つであるP53遺伝子の働きによる。)
しかし、癌細胞はこの機構に欠陥が生じているため、アポトーシスによる細胞死が起らない。
発癌の二段階説というのは、発癌の引き金に当るイニシェーションと、その促進の段階に当るプロモーションの段階に分けて考えるものである。
このイニシェーションを起すものがイニシエーターであり、フリーラジカル(活性酸素など)、ベンツピレン(タバコの煙やディーゼルエンジンの排ガスに含まれる)、ダイオキシン、ジメチルニトロソアミン(胃の中で、二級アミンと亜硝酸塩が反応してできる)などがある。
また、プロモーションを起すものがプロモーターと呼ばれるものであり、これとしては食塩(胃癌を促進)や胆汁酸(大腸癌を促進すると考えられている)などがある。
そして、発癌はこれらイニシエーターとプロモーターとがセットになって起こると考えられている。
したがって、イニシエーターだけ与えて発癌性を示さないからといって、それに発癌性がないということにはならない。
これにより毒性がかなり薄まるとされる。一口、30~50回くらいが目安のようだ。
ビタミンACEはそれぞれ抗酸化物質(抗酸化作用により活性酸素を消去できる)であるが、働き方が異なるため、これらを一緒に摂る方がよい。
活性酸素(主にフリーラジカル)は特に激しい運動を行なったり、紫外線を浴びたり、炎症が生じた場合などに発生する。
非発酵茶である緑茶はフリーラジカルの抑制作用が高く、発癌の抑制効果がある。
また、お茶や渋柿などに含まれるタンニンの一種であるエラグ酸には、ベンツピレン類の発癌性を抑制する効果があるとされる。
ただし、お茶(紅茶も含む)やコーヒーにはカフェインが含まれることから、過剰摂取は避けた方がよい。
緑黄色野菜にはビタミンAの前駆物質であるβ-カロテンなどのカロテノイドが含まれている。
カロテノイドは赤や橙、黄色などの色素の元になっているもので(これは電磁波のそれ以外の波長成分(特に紫外線)に対する吸収能があるということを意味する)、ポリフェノールと共に野菜や果物の代表的な抗酸化物質である。
(このようなものが植物に含まれるのは、植物が太陽光に照らされることによって生じる活性酸素を消去するため。太陽光は植物にとって光合成を行なうのに必要なものであると共に活性酸素を生じさせることになる諸刃の剣ということになる。なお、生体では太陽光はビタミンDの合成に役立つことになるが、細胞に損傷を与えたり、メラニン色素の増殖を促す諸刃の剣となる。)
動物性のビタミンA(レチノールのこと)は使用されなかったものは排出されるが(このため毎日、必要量を摂取する必要がある)、カロテノイドの場合には体内の要求によりビタミンAに変化することになり、過剰症の心配はない。
(ただし、ビタミンAに変化しないカロテノイドもあり、これとしてはリコピン、ルテインなどがある。なお、リコピンがカロテノイドの中では活性酸素消去能が最も高い。)
このため、レチノールよりもカロテノイドの方がビタミンAとしての利用性に優れる。
カロテノイドの摂取で注意すべきことは、単一のカロテノイドのみを多量に摂取しないことである。
というのは、そのことによって逆に抗癌作用が低下することもあるため。
また、β-カロテンを食物から摂取する場合とサプリメントから摂取する場合とで効果が逆になる場合もある。例えば、肺がんリスクの高い人がそれをサプリメントから摂った場合には、癌発症率が増大することが分った。
野菜からの摂取が難しい場合には野菜ジュースを飲むのもよい。
焼け焦げた魚肉にはアミン類が多く含まれていて、胃の中でこれと亜硝酸塩とが結合するとニトロソアミンができるが、これは強力な発癌物質である。
亜硝酸塩は発色剤や保存料としてよく使用される他、野菜や漬物に含まれる硝酸塩が唾液によって亜硝酸塩となる。
コウジカビの一種が産生するアフラトキシンは強力な発癌物質(肝臓癌を引起こす)であり、これはピーナッツ(主に熱帯産)やピスタチオに生える。
水道施設では殺菌消毒のために水源の水に塩素が加えられるが、これと農薬や家庭排水などで汚染された水源の水中に含まれるフミン質とが反応して、発癌物質のトリハロメタンが生じる。
特に、夏場の大都市の水道水は塩素臭が強く(これは近年、改善されてもいるようだ)、生でそのまま飲むのは危険性がある。
トリハロメタンを少なくするには、浄水器を用いるか、煮沸してこれを蒸発させる(5分程度)と効果がある。
喫煙は発癌原因の30%を占めるとされ、これは食事による発癌原因の35%に次ぐものとなる。
また、リポフスチン(これは葉脈での栄養分の流れを阻害して紅葉の原因物質となるもの)が脳に蓄積し、脳の衰えを招くとされる。
そのように喫煙の有害性はよく知られることになったが、タバコは嗜好性・習慣性が高いことから、禁煙に至らないことが多いようだ。
しかし、喫煙は自己のみならず他者の健康を損なうという意味では、(利己主義者でない限り)ぜひとも禁煙に踏み切るべきである。
飲酒の継続により酒に対する感受性が低下することになるが、このことは(必ずしも)酒に対する肝臓の解毒能力の向上を意味しているわけではない。したがって、やはり適量を守ることが望ましい。
なお、社会的には酒に強いことが同席の人達からの称讃を得たりするが、これは身体能力の高さ(主に遺伝子的なもの)を称讃しているというよりは、単に相手を酔わせてやろうという欲求を反映したものと考えられる。したがって、そのことは単に相手の「策略」に嵌まっていることになるのであるから、愚かなことであろう。ただし、相手に対して好感触を与える効果はあるだろう。特に、上司などに酒を勧められた場合、無下に断ると反感を買うことがある。(課長等の上級職に出世したといっても「人間が出来ている」ことは少ないだろう。)
ウイルスとは、単に遺伝子的実体(核酸のことで、つまりRNAやDNAのこと。DNAはRNAに翻訳されて実行されるのであるから、これらの働きは結果的には同じである)が蛋白質の殻に包まれたものである(さらに殻の外側に被膜(エンベロープ)を持つものもある)。
したがって、生物というよりは物質的なものであり、薬剤などによる撃退・排除が難しいという性質がある。
生体では、これを免疫系が認識して撃退することになるのだが、形態変化の激しいものや増殖が急速なものに対しては防御が難しい。
ウイルスは標的の細胞表面に付着し(このことはこれに適合する受容体の存在による)、核酸を入り込ませて、蛋白質を合成したり自身の核酸を複製させ、自己のコピーを多数作り、細胞外に放出することになる。
また、侵入された細胞の方はこのときに死滅してしまう。
ウイルスの中には核酸を宿主の細胞のDNAに入り込ませたりして宿主の遺伝子を変えてしまうものがある。
このようなウイルスは細胞の癌化を起すことにもなる。
(癌の2割はウイルスが原因と考えられている。)
これとしては、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルス(肝癌)、ヒトTリンパ好性ウイルス1型(HTLV-1)ウイルス(成人T細胞白血病)、EBウイルス(悪性リンパ腫)、パピローマウイルス(子宮頸ガン)がある。
また、インフルエンザウイルスやサイトメガロウイルスなども癌を誘発すると考えられている。
なお、ウイルスは唾液や性交渉などで感染するので気をつける。
(よく唾をつけて紙をめくったりビニール袋を開けたりする人がいるが、衛生的にはどうにも不安感を与えるものである。)
他には、ヘリコバクター・ピロリ菌が胃癌の原因となることが知られている。
これは強酸状態の胃の中でも棲息し得る細菌で、これが作り出す様々な分解酵素により胃の粘液層が破壊されて炎症を生じさせる。
また、細菌の感染によって動員された白血球による組織障害も起こる。
これらの結果、胃潰瘍や胃癌などが生じる。
ただし疾患が生じるのは、保菌者の3割程度とされる。
皮膚によるビタミンD産生のためには、夏では15~30分程度は日光に当たる必要があるとされる(ビタミンDは魚や卵、キノコなどに限られ、通常の食生活からでは欠乏しやすいビタミンである)。
それでも日差しの強い午前11時から午後2時の間は避けた方がよい。
特に顔を化粧していることが多い20代頃の女性では体内のビタミンDの数値が極端に低いとされ、したがってカルシウム不足による骨密度の減少は更年期以降に骨粗鬆症を引起す可能性が高い。
また、紫外線は日焼けの他にコラーゲン繊維を損傷し、この回復能力が低下する中年以降では皺の原因ともなり、容姿を特に気にする女性にとっては悩みの種となる。
また、クリームなどに使用される界面活性剤(多くは石油系の化学合成品)はシミなどを作る。
このことは、界面活性剤が皮脂膜を溶かすと色素や香料、防腐剤等の化学物質が表皮や真皮へ直接浸透することになり、この防御反応としてメラニン色素が異常に増えるためという。
オゾン層は大気上層部にできるオゾン(O3)によって形成されるもので、これは幅約20kmの帯状の層となる。
オゾン層に含まれるオゾンを1気圧で圧縮したとすると約3mmほどの厚さにしかならない。
オゾンは、太陽からの紫外線によって叩き出された酸素を含む分子からの酸素が、酸素分子と衝突することによってできる。
また、オゾンは紫外線によって分解されるため、効率よく紫外線を吸収することになる。
これらの紫外部放射線は波長250nm付近のもので、これは主にUV-Cとなる(UVとはultravioletの略)。
紫外線とは可視光線よりも周波数が高く(波長が短く)、X線よりは周波数が低い(波長が長い)電磁波のことで、すなわちこれは波長が10~400nmのものとなる。
紫外線は、大きく近紫外線(near UV)と遠紫外線(far UV)とに分けられる。
近紫外線は波長380~200nmのもので、遠紫外線は波長200~10nmのものとなる。
(また、波長10nm以下のものは極端紫外線と呼ばれ、これはX線の波長帯と重なる。)
近紫外線はさらに、波長400~315nmのUV-A、波長315~280nmのUV-B、波長280~200nmのUV-Cに分けられる。
DNAの吸収スペクトルは250nm付近となり、これはUV-Cに該当し、UV-AやUV-Bと比べてDNAを著しく損傷させるため皮膚癌の発生リスクが高いので、特に注意を要する。
遠紫外線は大気中の酸素分子や窒素分子によって吸収され、これは真空中でのみ進行するため、真空紫外線(vacuum UV)とも呼ばれる。
したがって、太陽からの紫外線として考慮するものは近紫外線となるが、UV-Cはオゾン層に吸収され地表には届かない。
また、UV-Bはオゾン層を通過するものの、地表に到達する紫外線の殆どはUV-Aである。
しかし、フロンが分解することによって生じた塩素によって多量のオゾンが分解されてしまう。
オゾン層が破壊されると身体に対する破壊作用が強いUV-Cが到達することになる。
家庭用電源の周波数である50Hzまたは60Hzは極低周波電磁波に分類され、これは国際がん研究機関(IARC)により、「発ガンの可能性有り」のランク2Bに指定された。
(このレベルには、他にはコーヒーや漬物、ガソリンエンジンの廃ガス等がある。)
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)により、電磁波への曝露は以下のように指導されている。
【50Hz:1G,60Hz:833mG,0.8kHz~150kHz:62.5mG】(Gはガウスで、磁界強度を表わす単位)
ただし、これは短期的曝露に関するもので長期的な曝露に対する制限ではないことに注意する。
メーカーによれば、『IHクッキングヒーターの磁界強度は商用周波数帯(50/60Hz)において50mG以下、加熱周波数帯(数10kHz)において20mG以下であり、国際的なガイドラインを大幅に下回っています。』ということのようだ。
ただし、小児の場合には2~4mG以上で小児ガンの発生確率が高まるとされる。
また、妊婦の場合には16mG以上で流産の可能性が高まるとされる。
電磁波は距離の二乗に反比例して弱まるため、電磁波発生源から離れればよいことになるが、それがどのくらいになるかといえば、IHクッキングヒーターの場合、30cm離れれば16~30mG以下となり、小児や妊婦を除く一般人の場合にはあまり問題がないようである。
ただし、何等かの身体傷害を感じたりする人の場合や、IHクッキングヒーターを囲んでの長時間の飲食は避けた方がよい。
また、IHクッキングヒーターを少ない油量で使ったり、鍋の底にわずかでも反りのあるものを使用すると油が発火して(油の発火温度は360度だが、使用が適正でないとこの温度に容易に達する)火災の原因となることにも注意する。
これは活性酸素の生成をできるだけ少なくするため。
ストレスは免疫力を低下させたり、活性酸素を発生させるため。
なお、他人を支配したり、他人を怒鳴りつけたり、他人にしつこく絡んだり(これは飲酒後のふるまいに多いが、これは飲酒によって日頃の抑制が解除されて本来の性向が露になるためと考えられる。これは酒乱として大目に見られることも多いが、恥ずべきことである。なお、人には集団欲なるものがあるとされ、無目的にも誰かにまとわりつくという傾向は一般的に見られるもののようである)、他人に嫌がらせをして楽しんだり、という人は少なくないが、このようなことでストレスを溜め込まないようにする。
このためには、そうした人またはその事態とはできるだけ関らないのが一番である。
もしそれが困難な場合には、その状況を改善するようにした方がよい。
これらのことも免疫力を低下させるため。
なお、睡眠促進物質はウリジンと酸化型グルタチオンであることが判明したという。さらに酸化型グルタチオンが生成される際、過酸化物質が分解されるという。過酸化物質は細胞を死滅させることにもなり、またニューロンは再生しないことから、睡眠は脳の健康を守るのに重要ということになる。
また、睡眠の初期に成長ホルモンがよく分泌されることから(これは身体の修復などにも関係し、子供だけでなく大人でも重要となる)、睡眠不足はこの働きを阻害することになる。
身体が冷えると血管が収縮して血液の循環が悪くなり、この結果、新陳代謝が低下したり、細胞に老廃物や有害物質が溜まり、細胞に悪影響を与えることになる。
このことは特に活発に活動している骨髄細胞などへの影響が大きくなり、免疫力の低下を引起こすことになる。(ただし、40℃以上の高体温でも免疫力は低下することになる。)
また、冷たい飲食物は胃の消化力を弱めることから、栄養不良に陥りやすい。
夏バテは暑さからというよりは主に冷たいものの食べ過ぎや飲み過ぎが原因していると考えられる。
アスベストは断熱材や車のブレーキなど広範囲に使用されていたが(特に昭和30年代から50年代(1955~1985)頃に建てられた公共建築物)、これは悪性中皮腫や肺癌の原因になるとして2004年に使用禁止となった。
肺癌はこの吸引後、肺胞に永久に留まって害を及ぼすことになり、5~10年経ってからこれらの症状が生じるとされる。
特に、喫煙が癌化を著しく進める(アスベストとの相乗効果で50倍ほど)とされる。
東日本大震災では地震や大津波により被災地に瓦礫が散乱することになったが、この処理では特にアスベストを吸引しないように注意する必要がある。(この吸引を防ぐには、単にマスクをするだけでは不十分で、マスクを重ねたり、曝露防止のゴーグルを着ける必要があるという。)
また、海中に溶けているアスベストを肺に吸い込むことによって肺炎が生じる。
因みに、アスベストと似たものにロックウール(岩綿)やグラスウールがあるが、これらは人造鉱物繊維で、繊維がこれらより(数十~数百倍も)細い天然鉱物繊維であるアスベストとは異なり、肺胞への吸引の危険性はないとされる。
実質的には歯磨き粉はあまり必要ではなく、歯磨きに問題があるとすればこの仕方の方にこそある。
なお、フッ化物は結合組織であるコラーゲンの合成を阻害するとされ、したがってこの老化(皺の原因)や破壊が促進されることになる。
ダイオキシンはヒ素の1000倍もあるほどの猛毒物質であり、これへの曝露は発癌や奇形などの障害を起す可能性が高い。
(なお、ヒ素でも無機ヒ素の毒性は強く、有機ヒ素の毒性は弱い。最も毒性が強いのは+3価の水溶性の無機ヒ素で、この致死量は0.1~0.3gとされる。因みに、水銀の場合には有機水銀の方が毒性が強いので、ヒ素とは逆になる。)
これは有機物と塩素を含むプラスチックを焼却する際にでき、この粉塵が環境中にばら撒かれる。
(また、芳香族塩素化合物の製造過程での副産物として生成されたり、トイレットペーパーや紙オムツ、紙パックなどの漂白された紙製品にも含まれる。)
このためダイオキシンは環境中に広く存在し、食物連鎖によって上位の生物に濃縮される。
これは生体では脂肪に蓄積することから、例えばマグロなどの大型魚の脂質の摂取は控えた方がよい。
また、食品群別では魚介類に最も多く含まれ、次に牛乳・乳製品、肉・卵、米、緑色野菜、と続く。
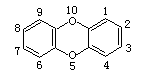
なお、ダイオキシンと似たものにジベンゾフラン(上図の中央の環がフラン環(10の酸素が取れた五員環)となったもの)があり、これも毒性が強い。
カドミウムはイタイイタイ病の原因物質としてよく知られているが、これには発癌性もあり、IARC(国際がん研究機関)により、コールタールやアスベストなどともに発癌性の5段階の分類(1,2A,2B,3,4)で最上位の「1」(人に対して発癌性あり、という評価)に指定されている。
またこれは人体での蓄積性もあり、この摂取や吸入はできるだけ避けた方がよい。
(ただし、この摂取源の主なものは日本では米であるとされ、この摂取量を減らすのは難しいようだ。)
カドミウムは電池(ニッカド電池)に使用されている他、顔料や塩化ビニルの安定剤としても使用されている。
このため、一般廃棄物焼却工場の焼却灰や飛灰にも高濃度に含まれているとされる。
カドミウムはIARCにより、ベンツピレンやクレオソート(木材の防腐剤)、ディーゼルエンジンの排気ガスなどとともに発癌性分類の「2A」(人に対しておそらく発癌性あり)に指定されているもので、この摂取はできるだけ避けた方がよい。
電子レンジは、これが発する2450MHzの周波数(これはマイクロ波に分類される)で水分子を回転させ、水分を含む食品に熱を発生させることで食品を温めるもの。
しかし、このようにして食品が熱せられた場合、フリーラジカルが発生し、これは発癌性がある。
また、たんぱく質の通常のアミノ酸であるL型アミノ酸(トランス型アミノ酸のこと。天然のものでは、不飽和脂肪酸の場合にはシス型になるが、アミノ酸の場合にはトランス型になる)がD型アミノ酸に変化するとされ、これには神経毒性や腎臓毒性がある。
なお、電子レンジの扉(これはレンジ内の電磁波を通さないとされるが)や密封材からは放射線が漏れているとされ、稼働中は2mくらい離れている方がよい。また、電子レンジが止まってから数分経った後で、取出すようにした方がよい。
因みに、携帯電話の電磁波もマイクロ波で、電子レンジと同じように水分を加熱するのではないかという疑問が生じるが、この周波数は800MHzで(ただし1500MHzや1900MHzを使用しているものもある)、これは水分子を加熱できるとされる1000~3000MHzの範囲外であるため、その心配はないようだ。
また、携帯電話のワット数は電子レンジに比べて遥かに小さいため、脳に悪影響を与えるとしても、かなり軽微であると考えられる。
もっとも、携帯電話を耳に当てて長時間使用するのは止めた方がよいようだ(特に子供の場合)。
発癌性物質が使用されていたり、人体にも有害であることが多いため。
戦後、合成洗剤は洗浄力が高いこともあって石鹸に代って多く使用されるようになった。
合成洗剤には様々な種類があるが、この中ではABSが洗浄力が最も高い。
このため、初期には洗濯用洗剤としてABSがよく使用されたが、これは分解性が悪く環境汚染の原因になるとして使用が取り止められた。
そこで、洗浄力がABSに次ぐLASが使用されることになった。
しかし、これはABSよりは分解性は高いものの、これが河川で半分に分解するまでには2週間ほどかかるとされ、環境汚染の問題は依然として残る。
人体ではLASには急性毒性があり、これを少し多量に飲めば死亡することがある(ヒトの推定致死量は20~30g)。
また、これには催奇形性や発癌促進性があるとされる。
ラットを用いた実験によれば、ある発癌物質のみを経口投与した場合には癌になりにくいが、LASと一緒に投与すると、高い割合で癌が発生した。
一般に界面活性剤は発癌物質の吸収を高めて発癌を促進させる、とされる。
そうした中では、台所用洗剤などに使用されるAE(POER)には催奇形性や発癌性及び発癌促進性はないとされる。
ただし、これは生分解性が悪く、環境汚染の原因となる。
また、台所用洗剤などに使用されるDA(脂肪酸アルカノールアミド)やAZは石鹸に近く、安全性が高いとされる。
PCB、フェニレンジアミン類(半永久・永久染毛剤に広く含まれる)などの発癌性物質が使用されている可能性があるため。また、美白クリーム・ジェルにはメラニンの生成を抑制するヒドロキノンが使用されているが、これはアレルゲンであり、発癌性も疑われている。また、神経を損傷する成分(「ケーソンCG」など)が含まれることもある。
また、一部の化粧品や点眼薬に使用されるチメロサールは毒性が強く、目に損傷を与えるとされる。
それに、一般的に結婚相手とするには相手の男性についてよく知る必要があるものであるが、このことは対象となる男性が身近な場所に限定されやすいものである。
そうであれば、美観が多少向上したとしても、男性の関心を高めることにはそれほど貢献しないと考えられる。
なぜならば、狭い範囲ならば認知度はいずれにしても高まる筈だからである。
また、そのことは自身についてもよく知られることになり、したがって外観よりも内面の方にこそ関心が高まるものであり(恋愛感情は鑑賞的というよりはメンタル的なものであるため)、単に外観のみを高めることはあまり効果がないと考えられる。
もし相手の男性が内面的価値を理解せず、外観のみの皮相的価値しか認めることができないような人であれば、結婚する価値はないといえる。
もっとも化粧によってかなり美人になるならば、一見的出会いから親密な交際に発展する率は高いと考えられ、対象範囲は広くなると考えられるが、このことを検証するためには、一年ほど社会実験をしてみるのが確実と思われる。また、そのようにして男性を獲得した場合、徐々に化粧度を低くして素顔に近づけるようにした方がよいと考えられる。美観は初期のインパクトを強めるだけのものにすぎず、これは持続的なものではないからである。
恋愛が結婚を目的とするという考えは女性側については当てはまるとしても男性側には必ずしも当てはまるとはいえない。
なぜなら、男性側では男女間の関係は恋愛と結婚において家庭生活を除けば大きな差がないからである。
一方、女性側では結婚した場合、大抵は子供を出産し、その育児や家事に追われるということになり、恋愛と結婚とでは大きな差が生じる。
(恋愛においても子供の出産があるが、その後も未婚ならば大抵の場合、育児に専念できるような環境がないことから、このような恋愛は否定される。つまり、結婚とは恋愛的及び生活的に男女間の関係を永続的に定めるものということである。そのように他者が自己の生活圏に深く関与するようになることから、欺瞞的な恋愛というものは成立しにくい。また、単に美観的なものは馴れによって容易に美的認識が低下していくものであり、外見の向上は結婚生活においてはあまり効果がない。)
そうした男性側の考えが恋愛を虚構的なものとしても容認することになるのであろうが、このようにして得られた結婚は幸福なものにはならないだろう。
外観の虚構による幸福性は虚構によって覆い隠されている素性が知られていない場合やそれを虚構として容認される場合について言えるものである。
そのように、化粧の効用については十分に研究されているとは言えない。
もっともこの研究が難しいのも確かである。
というのは、この効用が恋愛に限定されるのではなく社会的効用も含まれるため、社会が複雑になるほどこの研究も難しくなるからである。
また、美観に対する判定も一面的ではなく多面的となることも、その効用判定を難しくさせることになる。
例えば、一様な白っぽさが美の判定基準になる場合もあるし、小麦色の肌が美の判定基準ともなるのであるが、これらの判定は個々の主観あるいは個々の「社会的主観」に依存するものとなる。
ただし、確実であるのは情報的エントロピーの低い方が美的になるのであるが、これを高める要因としてはシミやソバカス、皺、傷痕があり(これらはランダム性や非対称性を高める要因となる。特に対称性の崩れは美観を損ないやすい)、これは一様に塗りたくることによって覆い隠され、このために有効なものが白っぽい化粧ということになるのだろう。
この意味では、化粧の絶対的必要感は主にそうした人から発するものと考えられる。
私見としては化粧が有効なのは接客業といったことに限られ、この効用を一般的なものと考えるのは間違っていると思われる。
周りに美人が満ちあふれていないということで嘆いたりする男性は、異性を獲得することが難しい男性、あるいはそれが面倒な男性に限られるのではないかと思われる。
なお、男女における化粧の非対称性はどのようにして生じているかといえば、男女ペアの形成が主に男性側から為されるということによるものだろう。
つまり、選択される側はその選択度を最大にするという必要性が生じるからである。
発癌性物質が使用されている可能性があり、しかもこれは衣類に残留するため。
ドライクリーニングに使用される溶剤(トルエン、トリクロロエチレン、ペルクロロエチレンなど)には人体に有害であったり、発癌性を疑われているものがあり、これは衣類に残留するため。
これは皮膚の脆弱性を高めるとされ、皮膚癌のリスクが高まる。
ミネラルオイルはボディオイルによく使用されるが、これは皮膚の呼吸や解毒能力等を阻害し、皮膚炎などのトラブルの原因となり得る。
ベビーパウダーはケイ酸マグネシウムのことで、タルクとも呼ばれる。
これらは発癌性物質であり、しかも吸い込むと肺に永久に留まるため。なお、猫の粘土タイプのトイレ砂の、粘土の粉末はシリカ粉塵のようだ。
家庭用洗剤、ヘアスプレー、エアゾール(式スプレー)、空気清浄剤(これに含まれる合成香料には喘息発作やアレルギー性接触皮膚炎などを起す可能性のあるものが少なくない)、殺虫剤(有機リン系殺虫剤、有機塩素系殺虫剤など人体にも有害なものが多い)、農薬(これは神経疾患との関係が深いとされる。また、この曝露は免疫力を低下させるようだ)、除草剤などを使用することで、これらに含まれる様々な揮発性または飛散性の化学物質により、屋内は屋外よりも毒性または発癌性物質の濃度が数十倍も高くなっているとされ、早朝など定期的に換気を行なった方がよい。
また、室内に鉢植えの観葉植物などを置くと、ホルムアルデヒドやベンゼンなどの濃度を減らすのに効果があるとされる。
ベンゼンは発癌性物質のため。また、これは骨髄毒性が非常に強いとされる。ベンゼンはラッカー、ニス、洗剤、香水、家具用つや出し剤などに含まれ、皮膚からも吸収される。
ホルムアルデヒドは成人致死量が22gとされる毒物で発癌性もあるが、脱臭剤、消毒薬、洗剤、シャンプーなど、家庭用品に広く使用される。
この曝露によって、鼻づまりや目のかゆみ、頭痛などを起こすことがある。
二塩化エチレンは塗装ニスなどに含まれる溶剤。毒性が強く、動物ではこの曝露によって胃癌、乳癌、皮膚癌を起すとされる。
また、塩化メチレンは工業用溶剤や塗料除去剤として使用されるが、これは発癌性があるとされる。
「テフロン」は調理器具の表面や食品の包装・包装紙の防汚コーティング剤、繊維表面の防水コーティング剤として使用されるが、これが加熱されてできる分解物としてはPOFAがあり、これには発癌性があると考えられている。
癌細胞に対する免疫機能ということでは、これは主に細胞性免疫機能であるリンパ球が受け持つことになる。
これにはT細胞とB細胞の2種があり、これらが協同して癌細胞等を撃退することになる。
T細胞は骨髄の造血幹細胞で生まれ、その後、胸腺に移り成熟することになる。
このとき自己の細胞の特徴を学習し、「自己」と「非自己」を認識することになる。
胸腺は胸骨の内側にある比較的小さな臓器である。
これは10代の頃に最も大きくなり、10代後半から小さくなり始め、40歳代では約3割くらいに縮小し、老人の頃にはほとんど無いに等しくなってしまうという。
このことが、特に老人において癌が発生しやすいことの理由と考えられている。
ラドンは全て放射性同位体で、ウランやラジウム等の壊変によって生じる。
これは希ガス元素であり、気体として存在することから、大気中に拡散することになる。
このため、これは肺癌や肺気種などの原因となり得る。
(アメリカ環境保全局(EPA)によれば、アメリカの肺癌死亡者数の11%(年間2万人)はラドンによるものとされる。因みに、肺癌は呼吸困難となり、かなり苦しいものとなるため、癌の中でも特に避けるべきものである。)
しかしながら、それらの疾患と放射性物質との因果関係の立証は困難であることから、法的に訴えることは困難を伴う。
また、そうであるから、それを政府等が明言するということもない。
したがって、各々がその危険性に対して(過剰反応とならないように配慮しながらも)十分な予防的措置を取ることが肝要となる。
例えば、アメリカのネバダ州において100回以上も行われた大気圏核実験では、この風下の住民(核実験場からこの方角の半径200km以内が対象のようだ。少なくとも60km以内では死の灰が降り積もり、これにより癌に罹る人が現れた)に対して以下のことが忠告された。
ラドンの他にヨウ素やセシウムも代表的放射性物質として挙げられるのは、これらは気化しやすいため、広範囲に拡散することに因るものだろう。
(これは雪のように降り積もる死の灰といった放射性降下物を洗い流すためと考えられる。)
放射性ヨウ素は乳幼児に甲状腺癌を起す確率が高い。
例えば、チェルノブイリの原発事故ではこの汚染地における15歳未満の甲状腺癌の発症率が通常の100~130倍になったとされる。
ただし、この半減期は8.04日と短いため、汚染地や汚染源が十分な期間を経れば(2ヶ月で放射性ヨウ素は約1/190、3ヶ月では約1/2600となる)比較的安全になると考えられる。
なお、ヨウ素は海藻に濃縮されるため、海洋の放射能汚染に注意する必要がある。
セシウムの場合、これは半減期が30年(セシウム137の場合。他にはセシウム134もあり、こちらは半減期が2.0年となる)であり、ヨウ素と比べるとかなり長いため、この内部被爆(体内被爆)をした場合には、長期間に渡ってこの影響を受けることになる。
(なお生物学的半減期は110日であることから、3年経過すると約1/150、4年経過では約1/800となるため、実質的には5年以上経てばほとんど影響がないと考えられるが、この期間内に細胞に発癌性が生じた場合にはしばらく経ってから癌が発見されることになる。)
放射性セシウムはβ線を放出して放射性バリウム(半減期は約3分)に壊変し、さらにこれがγ線を放出することになる。
セシウムはカリウムと同族の元素であることから、カリウムと置換しやすく、したがって筋肉(特に心筋)などに集まりやすい。
また、これは細胞内のミトコンドリアの機能を壊すため、心臓や脳の毛細血管に対する悪影響(心筋梗塞や脳梗塞、脳溢血など)についても注意する必要がある。
特にセシウム137は心筋に濃縮されやすく、しかも心筋は非常に寿命の長い細胞のため、心筋は遅々としてしか再生しないため、心臓病で命を落とすことが少なくない。
したがって、不整脈や心筋梗塞を患った場合には要注意となる。
晩発性放射線障害としては、癌や胎児の奇形がよく知られているが、他には胎児の精神遅滞も危惧される。
胎児の発育において、脳では妊娠後8週目から15週目にかけて小集団をなしていた細胞が遊走して脳の基礎的構造が形成されるが、このときに放射線に曝露されると、脳の形成に悪影響が生じて、精神薄弱児を生むことがある。
他には放射性ストロンチウムも毒性が強いため特に注意する必要がある。
この(物理的)半減期は29年で、生物的半減期も49年と長く、この実効半減期は約18年となる。
ストロンチウムはカルシウムと同族の元素であり、これはカルシウムと置換しやすく、骨などに蓄積されることになる。
骨に蓄積した放射性ストロンチウムはβ線を放出することから、悪性骨腫瘍(骨の癌のことで、骨肉種、軟骨肉腫、ユーイング肉腫などがある。特にユーイング肉腫は進行が早く悪性度が高いが、これは比較的稀な腫瘍である)や白血病の原因となる。
また、骨髄の障害により白血球の一種の好中球の減少が起こるとされる。この結果、免疫能力の低下が生じ、最悪の場合には敗血症(細菌感染が全身に波及したもの)になることがある(この防止には豆乳ヨーグルトの摂取が有効であるという)。
ストロンチウムが人体に入るルートは食物や飲料水となるが、特に海藻や魚、牛乳に蓄積されやすいとされ、これらの放射能汚染に注意する必要がある。
α線は高速なヘリウム原子核であり、これは正電荷を持つため数cmの空気層によって遮断されるとされる。
したがってこの悪影響は内部被爆によってもたらされる。
α線の放射線毒性は強いため、この放射性物質の吸入や経口摂取に注意する必要がある。
β線は高速な電子(負電荷を持ち、これは中性子のβ壊変によるもの)または陽電子(正電荷を持ち、これは陽子のβ壊変によるもの)の流れであり、物質によって遮蔽されやすい。
γ線は高い周波数(したがって波長が短い)の電磁波であり、このためα線やβ線と異なり、透過性が高い。
これは電磁波でもエネルギーが高いことから、X線と同じように化学結合に影響を与えることになる。
これによりフリーラジカルが発生して、遺伝子の複製に障害を与えることになる。
(化学結合に影響を与えるということでは可視光線でも起こるが、この場合の網膜での化学的変化は可逆的となることから、可視光線では無視される。一般に、紫外線以降の電磁波の場合に人体に対する影響が高くなるが、赤外線やマイクロ波のように可視光線よりも波長が長い電磁波の場合でも人体に対する影響が現れる。送電線のような低周波の電波源では、これは電磁波というよりは磁場が影響することになる。)
なお、内部被爆しているかどうかは「ホールボディカウンター」によって分かるが、これによって検出されるのはγ線のみとなる。
中性子線は電荷的に中性な粒子の流れで、この中性子は高速中性子と低速な熱中性子とに分けられる。
中性子線は粒子との衝突によって減衰するが、熱中性子の場合には高速中性子よりも反応断面積が大きくなるという特徴がある。
なお、プルトニウムはウランよりも1万倍も中性子を放出するとされ、これに伴ってα線などの他の放射線も放出され、比放射能の高いことがウランよりもプルトニウムの毒性が強いことの理由のようだ。
このことから、タンプリンとコプランの学説に基づいて、「耳掻き1杯で百万人が癌になる」ということが流布されたが、これは誇張した表現であって実際にはこれを支持するデータはないとされる。
しかし、プルトニウムが非常に危険性の高いものであることには変わりがない。
特にプルサーマル発電の燃料として使用されるMOX燃料はプルトニウムを5%ほど含んでいるとされる。
ただし、これが原発事故により、炉心損壊して水素爆発等が起っても、粉末や微粒子となって遠くにまで拡散することはないとされる。
このことはMOX燃料が陶器のように焼き固められているためという。
しかし、炉心融解が起きた場合には、この限りではない。
一方、ホルモンはこの内分泌腺から血管内に放出されて体内を隅無く巡り、細胞表面にこの受容器(レセプター)を持つ細胞(標的細胞)に働きかける。
この場合の細胞への作用は、特定の遺伝子に働きかけて、蛋白質の合成を促すことである。
つまり、これは特定の細胞のある機能の活動を促すスイッチを押すような物質ということになる。
ホルモン物質とレセプターとの対応関係は、鍵と鍵穴の関係に例えられ、ホルモンの形状に合うものがこのレセプターということになる。
したがって、ホルモンと似たような物質を体内に取込み、血中に流れ込むとこのホルモン作用が現れることになる。(ただし、エストロゲン様活性を持つ化合物の間での構造的類似性はあまり認められない。)
そのように体内の細胞が産生するホルモンと同じような働きを行なったり、それを阻害するような物質のことは内分泌攪乱物質と呼ばれるが、一般的にはより分かり易く環境ホルモンという名で呼ばれる。
そうしたホルモンの中で最も重大なのが、女性ホルモンの一つであるエストロゲン(卵胞ホルモンのこと。女性ホルモンとしては、他に黄体ホルモンであるプロゲステロンがある)で、これは卵巣から分泌され、子宮筋を発達させたり、子宮内膜を肥大増殖させて、受精卵の着床準備を行なわせるものである。
また、これは胎児の成長初期においては性分化を促すものとなる。
したがって、胎児(男児)や胎仔(オス)がエストロゲン様化学物質に曝露されると、生殖器奇形等の障害が現れる。
また、出生時にはその問題が現れなくても、第二次性徴期となる思春期頃に現れることもある。
また、エストロゲン様化学物質の過剰(身体で作られる量以上)な曝露は、癌を引起こす可能性があるとされる。
(特にエストロゲンは乳癌細胞の増殖を促進させることが多い。)
それに、他の物質との相乗効果により、それぞれ単独の場合よりも影響が強くなることもある。
女性ホルモンのような細胞間情報伝達物質がなぜ癌を引起こすのだろうかという大きな疑問が生じるが、これは次のことが関係しているようだ。
この代表的な疾患である乳癌については、この原因物質はエストラゲンの分解物質である16α-ヒドロキシエストロンであることが推定された。
これはDNAと不可逆的に結合して、遺伝子を損傷させる可能性が高いという。
もし、エストロゲンから16αへの分解を促進させるような物質があれば、この物質は乳癌リスクを高めることになる。
そこで、このような物質が探されることになり、これとしてはDDTやDDE(DDTの分解物)、アトラジン、PCBの一種、ケポンなどがあることが分かった。
エストロゲン様化学物質としては、フタル酸化合物(フタル酸エステルなど)、ビスフェノールA、アトラジンなどがある。
他には、化粧品に広く使用されているパラベン類も弱いエストロゲン作用があるとされる。
(また、化粧品用防腐剤として使用されることが多いイミダゾルニジル尿素はホルムアルデヒドを放出する可能性があるとされる。
ホルムアルデヒドはエタノールアミン類と反応して発癌性物質のニトロソアミンを生じる。エタノールアミン類としてはトリエタノールアミン(TEA)が挙げられ、これはシャンプーなどに使用される。)
フタル酸化合物は建材、化粧品、プラスチック(これには柔軟性を与えるために添加されるが、この分子はプラスチックから容易に分離し、溶出したり気化することになる)などに含まれる。
これは広範囲に環境や食品を汚染しているとされ、これへの曝露は微量であっても精子破壊、喘息、アレルギーなどを引起こす可能性があるとされる。(ただし、マウスやラットにフタル酸エステル(DEHPなど)を用いた生体内実験(in vivo)では精巣破壊等の生殖毒性が認められるものの、サルを用いた場合にはこの悪影響はないとされる。しかし、他物質との複合的なこと(カクテル効果)も考えるとこの証明は難しいと思われる。)
ビスフェノールAはポリカーボネート樹脂プラスチックやエポキシ樹脂などの成分で、耐熱性プラスチック容器であるフラスコや、ブリキ缶(内側にプラスチックをコーティングしてあるものが多い)などから溶け出す。
また、これは多くの河川を汚染し、それから取水した水道水にも微量ながら含まれることになる。
アトラジンは世界で最も多く使用されている除草剤の一つで、トウモロコシやサトウキビなどの生産に使用されているが、これはエストロゲンやプロゲステロン(黄体ホルモン)、プロラクチン(乳汁分泌ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン)などのホルモンバランスを崩すとされる。
世界中でカエルが激減しているが、このような両生類の個体減少はアトラジンによる環境汚染(これは雨粒に混じって広範囲に汚染している)が関係しているのではないかと考えられている。
アトラジンによる環境破壊などが危惧されているにもかかわらず、これが収量増(3~4%?)に寄与するため、この使用禁止措置を取っている国はほとんどないようである。
しかし、閉経後はエストロゲンの分泌が少なくなり、この弊害として更年期障害や骨粗鬆症が起こりやすくなることから、この場合にはエストロゲン様物質の摂取はそれらの症状を改善することになる。
エストロゲン様活性を持つ植物は他にも色々あることが分かり、それらの物質はイソフラボン類、クメスタン類及び酸性ラクトン類に分類される。
この中ではイソフラボン類が一般的であるが、この全てのものがエストロゲン様活性を持つわけではない。
イソフラボンを含む植物としては大豆がよく知られていて、イソフラボン類の中ではこのエストロゲン様活性は強いとされる。
しかし、日本などの東アジアの国では大豆は日常的に摂取されているにもかかわらず、乳癌等の発生率は欧米に比べてかなり低い。
したがって、必ずしも植物エストロゲンが乳癌等の発癌リスクを高めるわけではない、ということになる。
この理由は、大豆イソフラボンの一つであるゲニステインには、腫瘍細胞の増殖などを促進するチロシンキナーゼという酵素の働きを阻害したり、細胞のアポトーシス(細胞の自己死)を促進する作用のあることが関係しているようだ。
結局のところ、大豆製品の通常の摂取量では特に問題ないとされるが、乳癌に罹っている人の場合には避けた方がよい。
また、妊婦や乳幼児は摂取量を減らした方が良いようだ。
また、米国では他の国で禁止されている遺伝子組み換え牛成長ホルモン(rGBH)が使用されていることがことが多い(全米の牛の3割くらいが該当)とされるが、このホルモン投与牛のミルクには発癌性が指摘されている。このことはこのホルモンによって乳線炎に罹りやすくなり、膿汁が混入することや、この炎症を抑えるために抗生物質が投与され、これが残存していることが関係しているようだ。
このミルクや乳製品(アイスクリームなど)を摂取した場合、乳癌や大腸癌が発生しやすくなる危険性が指摘されている。
なお、腸などを調理する場合には十分に加熱した方がよい。
また、近年では牛にBSEという病気が発生し、これはヒトにも感染するとされるが、この危険部位としては脳や腸、脊髄などがあり、輸入牛を用いたホルモン焼きや脳みそ料理を食べる場合には注意を要するようだ。
因みに、BSEは凝集性を示す異常蛋白質であるプリオンが脳に到達して、中枢神経系が破壊される病気であるが、通常では蛋白質は血液脳関門でブロックされる筈なのでそうした病気はあまり起らないと考えられる。
都会などでは子供達が大声を出して遊んでいる風景をよく見掛ける。
これは親からすれば非常に元気があって良いと考えているかもしれないが、それがH-LD症によるものだとすれば非常に憂慮すべき事態といえる。
一般に大声を出して話すということは、大勢の人の前で話す場合や周りの者に対して自己の威厳性を示したい場合を除いては、自分の主張を強引に相手に認めさせたいか、相手の主張を強引に否定したい場合によく行われるわけであり、そうした傾向はそのような環境に陥っている人の場合(例えば、自分の考えが常に正しいと考えるような狭量な支配者に依存して生活している場合)によく形成されやすいものである。
という意味では、そうした性格は環境によって形成されていることが少なくないと考えられる。
しかしそのような傾向は一般的に多く認められ、このためそれは単に環境によって生じているだけとはいえない。
近年では子供達は多くの情報と接するようになったため(これは戦後の義務教育及びテレビの普及以後に顕著になった。また漫画文化が隆盛となったことも関係している)、過去に比べれば精神的発達は著しいといえる。
そうしたことから小さい頃から強力な自我が形成され、そのために強い自己主張が生じているのだとも考えられる。
したがって、そのような傾向が都会において著しいようなのは、情報過多に原因が求められるかもしれない。
或いは、言語的なことが関係するとも考えられる。
人間というのは感情的な生き物であり、その言動においては感情表現が非常に重要なこととなる。
つまり、人は物事を伝えるということだけでなく、自身の感情をも伝えるという傾向が強いのである。
例えば、相手の主張が正しくないということを言う場合、それを単に否定するだけではなく、相手を罵倒するということがよく為されるものである。
後者はすなわち自己の感情を相手に伝えようとするものに他ならない。
その点、東京の方言ともいうべき標準語は、理性的言葉であるが故に感情表現にはあまり向いていないといえる。
そこで、自己の感情を相手に伝えるためには、音声の強弱やイントネーション(これは文頭を強く発声するということに顕著である)によって行なうということになるのだろう。
しかしながら、彼等の会話に何の意義も見いだせない他人からすれば、それは動物的な「会話」となり、原始的なものに聞こえる。
原始的会話として代表的なのは赤ちゃんの泣き声である。
赤ちゃんは言葉を話すことができないために、自己の感情を伝えるためには泣き声でしか伝えることができない。
つまり、赤ちゃんは泣き声の強弱あるいは繰返しによって感情を伝えることになる。
そのことは感情的表現性に弱い標準語を話す状況とよく似ている。
例えば、テレビドラマではよく女性が金切り声を、男性は大声を上げることが多いが、これはそうすることによって感情を表わしたいからだと考えられる。
(しかし、標準語のそうした感情表現にあまり馴染みのない者からすれば、それは作為的なものに感じられ、奇異なものに思われる。)
この中ではタール色素がH-LD症の原因になるということについては永らく疑問であったようだ。
リステリア症はリステリア菌による中毒症状で、発熱や頭痛・悪寒・筋肉痛の他には、嘔吐などの胃腸炎を引き起すことがある。
重症になると、髄膜炎や敗血症を引き起こす。
特に妊婦が感染すると胎児に大きな悪影響が生じ、早産や死産、胎児の死亡あるいは胎児の髄膜炎・敗血症を起すことがある。
感染はリステリア菌に汚染された食物を食べることによって起こるが、リステリア症となる可能性はかなり小さい。
しかし、中にはリステリア症に罹りやすい人もいて、数時間後に発熱等の症状が現れたら、重症(数日~3週間後くらい)となる前に医療機関に受診する必要がある。
というのは、致死率が一割くらいになるからである。
リステリア菌は他の細菌に比べて加熱・低温(-4度でも繁殖可能)・塩・酸に強く、この発症リスクの高い人(妊婦や免疫不全の人、新生児、幼児、老人など)は、以下のことを心がけた方がよい。
界面活性剤とは水と油のように混じり合わないものを混ぜ合わせる物のこと。
これとしては石鹸が代表的であり、この成分は脂肪酸ナトリウムや脂肪酸カリウムとなる。
(なお、植物性油脂が70%以上のものが本物の石鹸という。)
しかし、石鹸では油汚れやカビを落すことが難しいことから、合成洗剤(合成界面活性剤)が広く使用されるようになった。
また、現在では洗濯は全自動洗濯機を用いて行われるようになったが、これは合成洗剤の使用を前提としたもので、粉石鹸を用いた場合には洗浄効果が落ちることになる(粉石鹸の使い方次第では、合成洗剤と同様な洗浄効果を発揮させることもできるが)。
合成洗剤の成分はABS(分岐型(ハード型)アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)やLAS(直鎖型(ソフト型)アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、AS(アルキル硫酸エステルナトリウム)などであるが、これは高い洗浄効果の反面、皮膚や内臓・胎児に対する有害性や、河川・湖沼などの環境汚染の問題が生じるようになった。
合成洗剤による手荒れの原因は、合成界面活性剤は皮膚への浸透性が高いのと(界面活性剤は皮脂膜を溶かし、さらにリン脂質で構成されている細胞膜を溶かし、細胞を破壊することになる)、これがタンパク質を溶かすため。
他には、石鹸が分解しやすいのに対して、合成界面活性剤は分解しにくいということも関係している。
このため、合成界面活性剤が体内に蓄積されていくことになり、その使用を止めても、この悪影響はしばらく(1ヶ月以上)残ることになる。
因みに、洗濯用洗剤成分としては、洗浄力は高いが泡が消えにくいことから環境への悪影響が顕著に分かるABSから、LASに変化することになったが、LASはABSに比べて洗浄力が劣ることになり、これを補うために様々な助剤が加えられるようになった。
この助剤も有害性があるものが多く、界面活性剤と併用することにより、この相乗作用が現れ、悪影響が強まるとされる。
(なお、タンパク質分解酵素も助剤として添加されることが多いが、これが効力を発揮するのは水温が40~50度とされる。)
しかし、ゼオライトにはアルミニウムが含まれ、しかも非常に小さい分子であるため血液脳関門をすり抜けて脳に侵入しやすいという特徴がある。
アルミニウムには神経毒性があるため、ゼオライトが体内に入ると神経障害を起す可能性が強まる。
近年はアルツハイマー病に罹る人が多くなったが、これはゼオライト入りの合成洗剤を使用するようになったことも一つの原因になっているのではないかと考えられている。
(他にはアルミ製の調理器具からのアルミニウムの溶出もこの原因として挙げられる。)
ライポンFはABSを用いた食器・野菜用中性洗剤であるが、これを粉ミルクと間違えて、この15グラムを誤飲した32歳の男性が死亡した。
これは父親が乳児にミルクを飲ませようとしたところ、乳児が飲むのを嫌がったため、試しに自分が飲んでみたからだった。
なお、そのような事態に至ったにも関らず、不思議なことにこの容器には「~ 毒性を有せず 衛生上無害」と書かれていた。
おそらく、このことは洗剤は水で洗い流すことを前提にしたものと考えられる。
したがって、高濃度の洗剤を15グラムも摂取することは考えられていなかったのだろう。
これは安全性における過大表記というべきもので、これは消費者に対して過剰な危惧を与えないようにするためのものと考えられるが、このようなことはこの取扱いにおいて消費者に安易な気持ちを抱かせるという意味では有害無益なことである。
ただし、自動洗濯機で粉石鹸を使用する場合の注意点として、次のことが挙げられている。
①最初に水洗いをする。
なお、合成界面活性剤は石油から作られるのが一般的であるが、ヤシ油などの天然油脂からも作ることができるため、天然の素材を使用していると謳われていても合成洗剤の有害性には全く変わりがないことから、やはり石鹸を使用する方がよい。
②洗剤の量を正しく計って入れる。これは洗剤の入れすぎは黄ばみの原因となるため。
③洗剤を水に入れる際には、水槽の水をかき回しながらよく溶かす。
④洗濯物は石鹸が泡立ち初めてから入れる。
⑤洗い終わり、脱水したら直に干して乾かす。これは黄ばみや臭いを防止するため。
それを避けるためには、できるだけ有機食品のものを選択した方がよい。
このことは農薬の害を避けるというだけでなく、有機栽培のものは栄養価が高まっていることから、栄養摂取の点でも利点がある。
(実際、野菜の栄養価は以前のものと比べて半減している成分(カルシウムなど)が少なくなく、これは農薬や化学肥料の大量使用やハウス栽培が原因と考えられる。農薬の使用が野菜などの栄養成分の低下を引起こすのは、これによって土壌中の各種生物(ミミズなど)や細菌を死滅させるからではないかと考えられる。)
なお、有機食品に切替え、農薬への曝露を減らすことは精子減少(これは胎児期での曝露の影響が強い)の抑制にも繋がり、不妊症の男性の症状改善に寄与することになる。
殺虫剤は害虫(ダニ類や線虫類)を駆除するためのもので、神経系に障害を与えるものが多い。
殺菌剤は細菌やカビなどを駆除するためのもの。これは、合成阻害剤(菌体構成物質の合成を阻害)と呼吸阻害剤(エネルギー物質であるATPの産生を阻害)とに分けられる。
除草剤は植物を枯らしたり、この発芽や生育を阻害するもの。このことは、光合成やタンパク合成を阻害したり、細胞分裂を阻害したり、ホルモン作用を攪乱させたりすることに因る。
植物成長調整剤は、果実を多くしたり大きくしたり、この落下防止などを目的とするもの。
分類 物質名 性質 備考 有機塩素系
有機塩素系は塩素を含む炭素化合物のこと。分解されにくいのが特徴で、環境中に残留し、生物に蓄積される。
また、毒性の強いものが多い。
DDT 強 C ○ 殺虫剤として大量に使用された。DDTは非常に分解されにくいが、一部はDDEに変化する。DDEも発癌性がある。 BHC 強 C ○ BHCも殺虫剤として大量に使用された。分解性が悪いため、環境中に残留している。 TPN ○ クロロタロニル。殺菌剤として多くの作物に使用される。
水洗いで落ちやすい。アルドリン 強 C ○ ハエやウジなどの殺虫剤として使用された。発癌性があるとして1975年に使用禁止となったが、海外ではまだ使用しているところがある。 ディルドリン 強 C ○ ハエ、カミキリムシ、ガ、シロアリなどの殺虫剤として使用された。 エンドリン 毒 D ◎ 殺虫剤として1954年から1975年まで使用された。 クロルデン 強 C ○ 殺虫剤として使用された。分解性が非常に悪いため、環境中に残留している。 2・4-D 中 △ △
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸。除草剤として広く使用される。
双子葉植物に作用してこれを選択的に枯らすことができる。
不純物としてダイオキシンを含むことがある。
PCNB 弱 ○ ○ 野菜などのネコブ病やタチガレ病などの防除に使用される。発癌物質のHCB(ヘキサクロロベンゼン)を不純物として含む。 オキサジアゾン 弱 B ◎ ○ 水稲、陸稲、ゴルフ場などの除草剤として使用。 クロルベンジレート 強 B ○ ハダニ類の駆除に用いられる殺虫剤。 ケルセン 弱 B ○ ジコホルとも。ハダニ類の殺虫剤。 プロピザミド 弱 A ○ 除草剤。 ネオニコチノイド 弱 ネオニコチノイドとはニコチンの分子構造と似た物質で、これにはアセタミプリドやクロチアニジン、イミダクロプリド、ジノテフランなどがある。これは神経伝達物質の一種であるアセチルコリン(主に末梢神経と筋細胞との情報伝達を行なっている)の受容体と結合する性質を持つ。
ただし、アセチルコリン受容体はムスカリン受容体とニコチン受容体の二つに大別され、ネオニコチノイドは後者のニコチン性アセチルコリン受容体と結合する。
昆虫がこれを摂取するとアセチルコリンの働きが阻害されて死ぬことになる。哺乳類の場合には昆虫に比べてこの受容体に対する結合率はかなり小さいため悪影響はあまりないとされるが、実際にはこの中毒症状(心臓の不整脈、動悸、痙攣、筋の脱力、皮膚疾患など)が起こることがあるとされる。
ネオニコチノイドは血液脳関門を通過することは少ないため、中枢神経系にはあまり影響を及ぼさないが、血液脳関門が十分に発達していない乳幼児では注意を要する。
特に日本ではこの残量基準が諸外国に比べて高いため(US基準では2倍以上、EU基準では10倍以上のものが多い)、この過敏体質の人は国産の果物やお茶に注意する必要がある。
また、昆虫の重要な働きとしては花粉の媒介があるが、蜂など昆虫の多くが死滅する事態になると、植物の受粉が為されなくなり、果樹などの農作物が実らなくなるという事態が生じる。
このことを憂慮して昆虫毒性の弱いジノテフランが用いられるようにもなったが、これを含む花粉で育った蜜蜂の成虫は方向感覚に異常を起すようで帰巣しなくなるとされる。このことは結局、蜂の集団生活を阻害してこの減少をもたらすことになる。
有機リン系
有機リン系は問題の多い有機塩素系に代わるものとして登場し、現在はこれが殺虫剤や除草剤の主流となっている。
しかし、これもそれほど分解性はよくないため、野菜や果物に残留していることがある。
DDVP 強 B ○ ○ ジクロロボスのこと。アブラムシ類やヨトウムシなどの殺虫剤。
揮発しやすいため、多量の吸入に注意する。アセフェート 弱 A ○ アブラムシ類、ヨトウムシ、アオムシなどの駆除に用いられる殺虫剤。 ダイアジノン 強 ◎ 殺虫剤。野菜や果物に残留していることが多い。水洗いや洗剤洗いでもかなり残留することが多いようだ。 MPP 強 B ○ フェンチオン。殺虫剤。 スミチオン 弱 B ○ フェニトロチオンのこと。殺虫剤として広く使用される。急性毒性は弱いとされるが、中毒による死亡事故がある。 マラソン 弱 B ○ マラチオンとも。殺虫剤としてよく使用される。また、ポストハーベストとしても使用される。有機リン系であるが、分解性が非常に悪い。また、精子減少の問題がある。 パラチオン 毒 B 殺虫剤。中毒事故死が多発したため、日本では1971年に使用禁止となった。しかし、外国では使用が許可されているため、サクランボなどに残留していることがある。 EPN 毒 B 害虫駆除用に広く使用される。 ピレスロイド系
ピレスロイド系は除虫菊の殺虫成分であるピレトリンに似た化学構造をもつもので、殺虫剤として使用される。
ペルメトリン 弱 C ○ 野菜や果樹の害虫駆除に使用される。また、家庭用殺虫剤の主成分として使用される。急性毒性は弱いが、魚毒性は強い。 シペルメトリン 強 C ○ 野菜や果樹の害虫駆除に使用される。 カーバメート系
カーバメート系は炭素・窒素・水素・酸素からなるカーバメート結合をもつもので、タンパク質の合成を阻害する。
殺虫剤や除草剤に使用される。
これは胃の中でハムなどの発色剤として使用される亜硝酸塩と結びついて発癌物質のニトロソ化合物ができやすい、とされる。
なお、チオカーバメイト系のものは光過敏性皮膚炎やアレルギー性皮膚炎を起こす。
NAC 強 B ○ ○ 殺虫剤として広く使用される。水洗いで落ちやすい。 ジネブ 弱 A ○ ○ 野菜や果物のサビ病やタンソ病の予防に使用される。 ベノミル 弱 B ○ ◎ ベンゾイミダゾール系の殺菌剤で、様々な病気の防除に使用される。 チオファネートメチル 弱 A ○ ベンゾイミダゾール系の殺菌剤で、様々な病気の防除に使用される。分解しにくいため、作物などに残留しやすい。 マンネブ 弱 B ○ ○ コクテン病、アカホシ病、エキ病、ベト病、サビ病などの防除に使用される。
不純物として発癌性及び催奇形性のあるETU(エチレン尿素)を含む。マンゼブ 弱 B ○ ○ マンコゼブとも。コクテン病、アカホシ病、クロホシ病、ツルガレ病などの防除に使用される。不純物としてETUを含む。 メソミル 強 B ○ △ アブラムシ類、ヨトウムシ等の殺虫剤として使用。 IPC 弱 A △ クロルプロファムのこと。除草剤。また、ポストハーベストとしてジャガイモの発芽防止にも使用される。このため、ジャガイモの残留基準がかなり甘くなっている。 アミノ酸系
グリホサート 弱 A ○ アミノ酸の合成を阻害する。除草剤として広く使用される。分解性が悪いため、土壌にしばらく残留する。 その他
パラコート 毒 A ○ ビピリジン系の除草剤。急性毒性が強く、解毒剤がない。農薬中毒死の大半を占める。 ジクワット 強 ビピリジン系の除草剤。変異原性あり。パラコートと同じく解毒剤がない。
土壌中では直ちに活性を失う。このため、収穫前のジャガイモの地上部の除草剤として使用するところもある。これによりジャガイモの皮が硬くなり、傷みにくくなるという効果もある。D-D 中 ○ 殺線虫剤で、広く使用される。
D-Dはジクロロプロパンのことで、D-D、D-D92、テロン92などがある。
塩素の結合の仕方により、1,3-ジクロロプロパンと1,2-ジクロロプロパンがある。D-Dは前者を55%含むもので、D-D92やテロン92はこれを92%含むもの。EDB 強 A ◎ 二臭化エチレン。1984年頃まで土壌用殺虫剤や燻蒸剤として盛んに使用された。発癌性の他、生殖器への悪影響(精子減少など)がある。 キャプタン 弱 C ○ ○ フタルイミド系の殺菌剤。水洗いで比較的よく落ちる。 アトラジン 弱 A ○ ○ トリアジン系の除草剤。
分解しにくいため、土壌に長く残留する。トリフルラリン 弱 B ○ ○ フッ素含有除草剤。 MCP 弱 B ◎ ○ フェノキシ酸系の除草剤。分解しにくく、土壌に残量する。 カルベンダゾール 弱 A ○ ○ MBC。分解性が悪く、土壌に長く残量する。 臭化メチル 強 A ○ 燻蒸用の殺虫・殺菌剤として使用される。多量の吸入により、目眩い、嘔吐、頭痛、呼吸困難などを起す。 ダミノジット 弱 A ○ 植物生長抑制剤で、リンゴの落下防止、ぶどう(巨峰など)の着粒増加に使用された。発癌性が指摘されて、メーカーが販売を中止したが、これは不純物として含まれるジメチルヒドラジンが原因のようだ。 マレイン酸ヒドラジド 弱 A ○ 植物生長抑制剤で、ジャガイモやタマネギの発芽防止、芝の生長抑止などに使用される。不純物として発癌性のヒドラジンを含む。 アミトラズ 中 B ○ ダニ類の駆除用殺虫剤。
亜硝酸塩と反応してニトロソ体ができ、これによる発癌性の問題もある。ダイホルタン 弱 C ○ カルボン酸イミド系の殺菌剤で、最も多く使用される。 アシュラム 弱 A ○ 除草剤。 リニュロン 弱 A ◎ 広葉雑草一般の除草剤。発癌性が最も強い農薬とされる。 アラクロール 弱 B ○ イネ科の雑草駆除に使用される。 CNP 弱 A △ 除草剤で、主に水田に使用される。不純物としてダイオキシンを含む。
CNPに汚染された河川を取水源とする水道水にこれが含まれ、この長期摂取により胆道癌のリスクが高くなったという疑いがある。