|
トルファン〜ウルムチ( '88 ) 酒泉〜敦煌( '88 ) 西安〜蘭州( '88 ) |
◇ 祁連山を仰ぐ
西安から酒泉までは列車で一日半かかる。 夜出ると着くのは翌々日の朝になる。 もちろん飛行機も飛んでいるが、今度の旅ではできるだけ飛行機を使わないで行こうという方針に決めていた。 帰りは上海から日本まで船便の予約を入れていたので、 旅程中一番西のウルムチから日本まで、空を飛ばずにひたすら地面を移動し、 海を渡って日本に帰り着こうじゃないかと考えたのである。 そしてそうすることによって、ウルムチが東京から4000km以上も離れているということを、 時間的にも空間的にも実感したかった。シルクロードの遙かなことを身をもって体験したかったのだ。
一晩通路に座り込んで、次の日の朝、蘭州で空いた席を筆談相手の女の子たちが取ってくれた。 新たに同席となった人達が物珍しげに私を見る。 女の子たちが私のことを説明する。 彼らは私に話しかけてくるが、解らないのでメモ帳を差し出す。 そしてまた筆談が始まってしまうのだ。
彼らは好奇心旺盛である。 外国人がめったに乗らない硬座車にひょっこり紛れ込んだ、 顔付きは同じなのに言葉の全く解らない異邦人に対して、 遠慮のない好奇の目でしげしげと眺め、話しかけ、 退屈しのぎに出してある私のガイドブックや文庫本を、珍しげに手に取り、 漢字交じりの日本語文を眺め、判るところだけ声に出して読んだりしている。 私が漢文は何とか理解できると知ると、 何とかして意志を通じさせようと一生懸命漢字を書いてくれる。 そして私が解るまで、文章を書き換えたり、辞書を引くのを手伝ってくれたりして、 辛抱強く待っていてくれる。 一般の日本人には、外国人を見て興味を持ってもわざと無視したり、 日本語や日本のことなんてどうせ外人には解らないだろうと決めつけてしまうような所があるが、 彼ら中国人にはそういう所はない。 何のてらいもなく自然に接している。
また彼らはとても親切である。 食べ物を恵んでくれたり、お湯の心配(1)をしてくれたり、 いろいろ世話を焼いてくれる。 中国に来て最初に驚くことは、物を買ったり切符を買うとき、 店員や駅員の態度が物凄く悪いことである。 「これいくら?」と聞いているのに、物憂げな目を向けぶっきらぼうに答えてくれるのはまだいいほうで、 物は投げてよこすし、客に少しでも気に入らない所があると、 噛み付かんばかりにまくし立てたり、プイと横を向いたまま返事もしてくれなかったりで、 こっちも腹の立つことばかりだ。 特に若い女の子がひどい。 店員や駅員は若い女の子が多いので、何か物を買うときはいつも不機嫌な女の子と応対しなければならない。 これは社会主義の悪弊というもので、彼らにはサービスを売るという概念が全くないのだからどうしようもない。 私の隣でニコニコしている親切な女の子たちを見ながら、 この人たちも仕事をしているときはあんなふうに不機嫌なのかなぁと考え込んでしまった。 どうしてこんなに違うのかなぁと……。
車窓の風景はゆっくり変わっていった。 朝、蘭州を通過する頃は黄色い黄土高原(2)のただ中を走っていた。 黄色い山肌と青い空のコントラストがとても鮮やかだった。 それから茶色い黄河の流れを渡り、緑の草原に包まれたなだらかな山々を登って行き、 モンゴルのように羊の群れがいる緑の高原地帯を抜けると、 今度は乾いたゴビ灘が広がる河西回廊に入って行く。 やがて夜になり、平原の上にたくさんの星が瞬いていた。
ずっと座りっぱなしでお尻が痛かったが、通路に座り込んでいる人もたくさんいたので、 硬い直角椅子でも座れるだけましとひたすら我慢して、 眠ったり起きたりしている間に夜が明け、大平原の向こうから朝日が昇ってきた。 反対側の車窓にはもう雪を戴いた祁連山脈が見える。 程なく酒泉に着く。
皆に別れを告げて列車を降り、バスで市内に向かった。 街の真ん中にある鐘鼓楼まで行き、酒泉賓館のドミトリー(相部屋)に宿を取った。 ここのドミトリーは25人部屋で、広い部屋にベッドがずらりと並んでまるで病院のようだ。
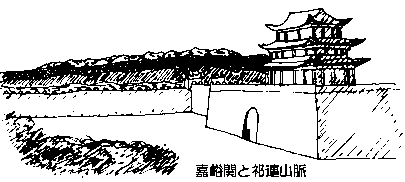
早速、隣町にある嘉峪関という明代のとりでを見に行く。 嘉峪関は万里の長城の終着点(3)である。 現在残っている長城はほとんど明代の物だそうだが、その西の果てにこのとりでが造られた。
嘉峪関市のオアシスを出てゴビ灘を少し行くと、 直ぐに高い城壁の上に立派な中国風の楼閣をのせた嘉峪関が現れた。 小高い丘の上にあるとりでは城壁が二重に巡らされ、 内城の二つの門と向こう側の外城の門の上に楼閣が建てられていた。 内城の門をくぐると中は四角い広場になっていて、平屋の建物が二つ三つあるだけだ。 両側の門の脇に坂道があって、城壁の上に登れるようになっている。
高い城壁の上に上がるととても見晴らしがよい。 南に祁連山脈を仰ぎ、北には黒い岩山が広がっている。 そして西は遙か彼方までゴビ灘が続いている。 内城の城壁は修理中で足場が組まれていることと、 東側を望むと工場の煙突が立っているのが興ざめで残念だったが、 昔、この雪を戴く祁連の山並みと城壁と楼閣の写っている美しい写真を見て、 ここへ行ってみたいと思っていたその願いは果たすことができたのだ。
次の日も朝から嘉峪関へ行った。 空は雲一つなく晴れ渡り、白い祁連の山並みがとても美しい。 一元を払うと楼閣の上に登ることができた。 城壁より更に高い楼閣の上から眺めると、祁連山脈の方に向かって長城がずーっと延びているのが見えた。 あの山々やゴビの平原や長城は、このとりでが造られたときとあまり変わっていないはずだ。 ここに拠った将軍や兵士たちも、毎日今と同じ祁連の山々を見て暮らしていたに違いない。 そんな事を考えていると、 城壁の回りの平原に兵士や馬や天幕の並んでいる様が見えるような気がした。
半日嘉峪関でのんびり過ごし、午後は博物館を見たり、 酒泉の有名な土産品である夜光杯(4)を買いに行ったりした。 翌日はいよいよ中国で最も有名な仏教遺跡の一つである、莫高窟のある敦煌へ発つのだ。
出発の日、まだ暗いうちに宿を出てバスに乗った。 デラックスバスというだけあって、普通の乗合バスに比べると格段に良いバスである。 出発して直ぐに夜が明けてきた。 嘉峪関を過ぎると、地平線からきれいな朝日が昇ってきた。 祁連の山並みはバラ色に輝きとてもきれいだ。 もう再びこの美しい山々を見ることはないかもしれないと思うと、少し感傷的になって、 心の中で再見と言いながらいつまでも山々を見ていた。 バスはゴビ灘や草原や岩山が次々と現れる変化に富んだ景色の中を快調に飛ばして行った。
|
| (C)Copyright 1998 ShinSoft. |
次へ |